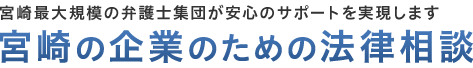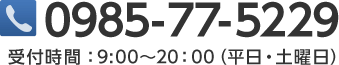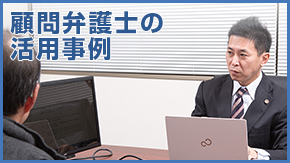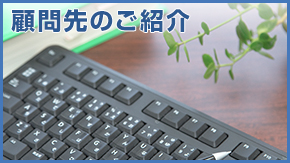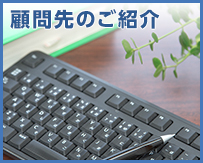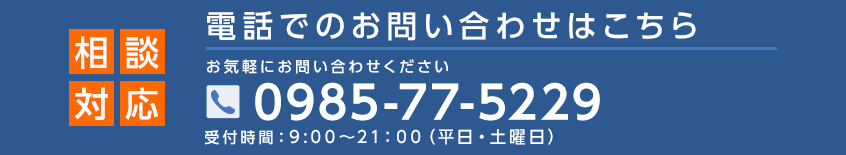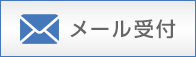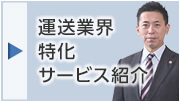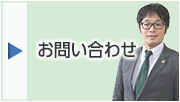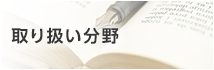建設業における未払い残業代の請求について弁護士が解説
今回は2024年4月以降に時間外労働についての上限規制が建設業にも適用されるようになりましたので,建設業において社員または元社員からの未払い残業代請求が増えるのではないかと心配されている経営者の方が多いと思います。そこで,今回は建設業における未払い残業代の請求についてお話ししていこうと思います。
お話しする項目は以下のとおりです。
1 建設業における未払い残業代問題の現状
2 残業代の計算方法
3 未払い残業代を請求された際の対処方法
4 弁護士に依頼すべき理由
5 当事務所のサポート内容
それでは早速内容に入っていきましょう!
1 建設業における未払い残業代問題の現状
時間外労働の上限規制が法律上は存在しない時代が長く続いていたのですが,時間外労働の上限は月45時間・年360時間とする法改正がされて,2019年4月1日から施行されていますが,中小企業に対しては適用が1年間猶予されて2020年4月1日からの施行となっていました。
 (厚生労働省「時間外労働の上限規制わかりやすい解説」より引用)
(厚生労働省「時間外労働の上限規制わかりやすい解説」より引用)
また建設業や自動車運転の業務(ドライバー)については2024年3月31日まではこの上限規制の適用がされない状態にありました。
しかし2024年4月1日以降である2025年3月現在,既に建設業についても時間外労働の上限規制の適用が始まっているということになります。
ただ時間外労働の上限規制の適用があるかどうかが,建設業における未払い残業代請求
トラブル増加につながるという関係にはありません。労働基準法に違反すると刑事罰の対象になり,また刑事罰を受ける事態になった場合には公共工事の受注などにも影響する可能性があるために,より注意が必要になったという面はありますが,上限規制の適用によって労働者が会社に請求できる賃金の額が増えるわけではありませんから未払い残業代請求トラブルが増える関係にはないということです。
しかし建設業においては未払い残業代請求のトラブルが生じやすい実情があると考えています。
1つ目は移動時間の評価が問題になることです。建設業においては複数の現場を同時に請け負うことも珍しくなく,現場で働く従業員については会社から現場まで(直行直帰の場合には自宅から現場まで)の移動時間をどう評価するのかが問題となるからです。
基本的には会社から遠い現場であっても現場での作業開始時間が始業時間,現場での作業終了時間が終業時間と考えることになります。会社から現場までの移動時間についての
従業員の負担は手当の支給等でカバーしていることが多いと思いますが,例えば会社から
複数の従業員が会社の所有する車両に乗って相乗りで現場に向かう場合に運転を担当する従業員について運転する時間を労働時間と評価する余地があるのではないかと考えます。
また現場近くまで移動してから現場での始業開始時間までの間の時間について従業員側からその時間も会社の指揮命令下にあるから労働時間であると主張されたことがあります。
そのケースでは現場近くに早く着いた後,現場での始業時間までは自由に使ってよい時間なで労働時間ではないと会社側は主張し,その主張を裁判所に認めてもらいましたが,
現場への移動を伴う従業員が多い建設業においては,このような問題が生じるというわけです。
2つ目は労働時間管理の問題です。建設業においても総務部などの内勤事務職の従業員についてはタイムカード等での労働時間管理がしやすいのですが,現場での監督や作業に従事する従業員については出勤時にタイムカードに打刻,退勤時にタイムカードに打刻といった対応を要求するのが現実的でないケースがあります。
特に現場での監督,作業に従事する社員については事業所から現場までに距離があり,
かつ社員の自宅から現場までの方が近い場合には直接行ってもらった方(直行の方)が社員の負担が少ないケースもありますし,現場からの帰りも同様です(直帰を認めた方が合理的という意味)。例えば事業所が宮崎市にあり,社員の自宅が高鍋町,現場が延岡市といった場合に事業所に1度出勤させてから現場に向かってもらうのは不合理だと思いますので直行,直帰を認めるケースもあると思います。

(宮崎県のホームページより地図を引用)
従業員に現場への直行,直帰を認めた場合には,その移動時間を労働時間と評価して主張する従業員は自宅を出た時点を直行のパターンの労働の開始時間,自宅に帰った時点を直帰の場合の労働の終了時間とする主張が従業員側から出てくる可能性があることに注意が必要です。
また各現場に会社がタイムカード等を置くこと自体が合理的ではありませんので現場での労働時間をどう評価するのかという問題があります。会社側としては現場ごとに決まっている作業開始時間に就労を開始し,作業終了時間に就労を終えたと主張することになりますが,従業員側から作業開始前の準備時間があり,それも労働時間であるという主張や作業終了時間の後に片づけを行っており,それも労働時間であるという主張が従業員から出てくることは避けられないところです。
会社によってはスマホのアプリやグループLINEで作業開始時間や作業終了時間,会社や自宅を出た時間,作業終了後に会社や自宅に帰った時間を報告されるところがありますが,従業員が実態と違う報告をしている場合にそれをベースにした労働時間の主張が行われ,それが認められるリスクもあることに注意が必要です。特に前述の直行・直帰を認めた場合にリスクが大きくなります。
以上をまとめますと建設業において未払い賃金請求のリスクが高い理由は,内勤の一般事務を担当する社員以外は事業所以外で働いている時間が長く,現場への移動を伴うことが多いことから移動時間の評価,労働時間全体の管理の面において争点が生じる部分があり,この点もあって従業員からの不当な未払い賃金請求を招きやすいという点にあると考えます。

2 残業代の計算方法
建設業だから特別な計算方法をとるわけではありません。
法定時間外労働(週40時間,1日8時間の法定時間を超えた労働)に対して発生する賃金は、1時間あたりの賃金の25%増となり、「1時間あたりの賃金(時給)×1.25(割増率)×残業時間」で算出します。1時間当たりの賃金は、「月給÷所定労働時間÷所定労働日数」で求めます。なお、月給には、家族手当・通勤手当・住宅手当などは含まれません。
3 未払い残業代を請求された場合の対処方法
建設業であるから特別な対処方法が必要になるということはありません。
以下の対処を心がけましょう。
(1)元社員等本人からの請求の場合
社員,元社員から請求されている未払い賃金の額とその計算根拠,労働時間をどのように
評価して計算されているのかを確認しましょう。口頭での請求ですとこの辺りが正確に確認できませんので文書で提示してもらう必要がありますし,社員,元社員(以下,「元社員等」といいます。)が作成した通知書(未払い賃金の請求を内容とする文書 タイトルは請求書であることもあります)を確認してもどうして請求額がその数字になっているのかがわからないケースもあります。
このように請求している額は明示されているものの労働時間をどのように考えて,どう計算した結果,現在の請求額になっているのかがわからないものが多いのが,元社員等本人が作成した通知書の特徴であり,会社としては元社員等に対して労働時間をどう評価して,どのような根拠で計算した請求なのかを元社員等に対して文書で回答を求めて,回答内容を踏まえて支払うべきだと考えた場合には支払うという対応になるかと思います。
未払い賃金を支払う際には元社員等と会社との間の未払い賃金請求をめぐるトラブルがその支払いで終わりであること,支払方法と支払期限,元社員と会社との間には今回支払う未払い賃金の外に何らの債権・債務がないことを確認する条項(清算条項といいます。)を入れた合意書を作成し,合意書に双方が署名・捺印した後に支払うようにしてください。
(2)元社員等の代理人弁護士からの請求の場合
この場合,未払い賃金の計算をして請求してくるケースはまれであり,労働時間の算定,未払い賃金の計算に必要な資料(就業規則,賃金規定,タイムカード,業務日報等)の提示を求める文書を最初に送ってくるのが通常です。
この文書を踏まえて会社としては提示を要求されている文書を提示する(コピーを郵送る)というのが通常の対応です。なお,元社員等の代理人弁護士から提出期限を切られていてその期限までに時間がない(提示書類の準備が間に合わない)というケースが稀ではありません。
この場合には提示する書類の準備ができる時期を明示して「令和〇年〇月〇日頃までに貴職の事務所に写しを郵送する形で提示しますので今しばらくお時間をいただけると幸いです。」等の記載した文書を弁護士の所属する事務所にFAX送信して,会社側が提示すると指摘した期限までに元社員等の代理人弁護士の事務所に届くように書類を郵送しましょう。
郵便事情も考えてその日までには文書の写しを必ず到達させることができるであろう期限を会社側で設定して,そこに向けて提示の準備をすることです。
文書を提示すると元社員等の代理人弁護士が計算をして未払い賃金の額を特定して文書で請求してきます。この文書を確認して計算根拠や労働時間としてどの時間までを評価したのかがわからない場合には質問して不明点を解消しましょう。元社員等の主張するままに根拠がない労働時間を労働時間として賃金計算してくることも稀ではありませんし,弁護士が作成したものであるからそれが正しいと考える必要はありません。
弁護士は依頼者のために動くものであり,未払い賃金請求の相手方である会社の利益を考えてくれるわけではありません。
未払い賃金の支払い額について折り合いがついた場合には合意書を交わして,その後に未払い賃料(合意書上は抽象的に「解決金」とすることもあります)を支払って終了なのは元社員等本人から請求があった場合と同様です。会社側が代理人を立てずに対応した場合,合意書は元社員の代理人弁護士が作成することが多いですが,この合意書もきちんと確認して署名・捺印するようにしてください。少しでも疑問な点があれば,この内容で署名・
捺印しても大丈夫かどうかを弁護士に相談することをお勧めします。
4 弁護士に依頼すべき理由
未払い賃金(未払い残業代)を元社員等から請求されている場合,代理人弁護士から請求されている場合,請求されているという状態がストレスになると思います。請求に応じない
場合には裁判や労働審判を起こされるかもしれない,労基署に駆け込まれるかもしれない,など不安な状態を解消するためにも弁護士に相談した方が良いと思いますし,このような心理的な負担を軽減するために弁護士に交渉を依頼する意味があると考えます。
また会社が自ら対応するとなると担当者がそのために時間をとられる,本来の業務が
所定労働時間内にできなくなり残業が発生する等の経済的な負担が生じることもあり得ます。
そして会社が自ら対応すると本来は応じる必要がない請求に応じてしまうリスク,適切な反論や質問ができずにうやむやなまま何となく金額を支払う形での解決になってしまう
リスク,解決時にきちんとした文書を交わしていないことから「実は他にも未払い賃金が
あった」として後日,それまでは請求されていなかった未払い賃金を請求されるリスクがあります。
このようなリスクは交渉にあたって会社側が代理人弁護士を立てることで避けられます。

5 当事務所に依頼するメリット
当事務所は建設業を含む100社以上の顧問先からの相談やその依頼に基づく事件処理を日常的に行っており,交渉段階,交渉が決裂した場合の裁判等の法的手続きにおいても豊富な経験と実績を有しております。
また,顧問先以外の法人,個人事業主からのスポットでの相談や案件対応についても行っております。建設業を営んでおられる会社,個人事業主の方からの相談や案件対応の依頼も少なくありません。
それでは未払い賃金請求(未払い残業代請求)はもちろん,労働者への対応にお困りの建設業を始めとする会社経営者,個人事業主の皆様,当事務所へのご相談,ご依頼を検討されてはいかがでしょうか。

文責 弁護士 浜田 諭
- 退職代行を使われたらどうする?対応のポイントについて弁護士が解説
- 円満退職を叶える退職勧奨のポイント|企業法務に詳しい弁護士が解説
- 債権回収を弁護士に依頼するメリットと判断基準について解説
- 既に退職した社員から現場への直行直帰を伴う就労について現場への移動時間、現場からの戻り時間についても労働時間であり、この時間について賃金が支払われていないことを理由に未払い賃金を請求されたものの元社員の請求額を大幅に削った内容の判決から付加金を削った内容にて控訴審が判決を下し、これが確定して解決した事例
- 懲戒解雇とは?懲戒解雇が認められる場合、認められない場合について、弁護士が解説
- 【ご報告】代表弁護士柏田笙磨が国際ロータリー第2730地区の危機管理委員(弁護士)に選任されました
- 解雇の種類と注意すべきポイントを弁護士が解説
- 問題社員について解雇するのではなく交渉によって会社都合退職という形で合意退職による解決ができた事例
- 遅刻や欠勤を繰り返す問題社員を放置するリスクとは?企業が知っておくべき対応方法について弁護士が解説
- 業務の指示に従わない社員にどう対応する?問題社員対応について弁護士が解説