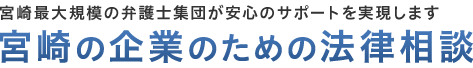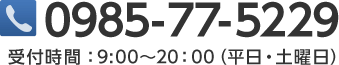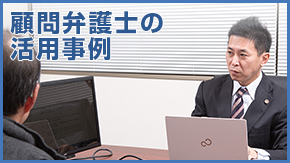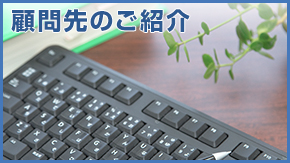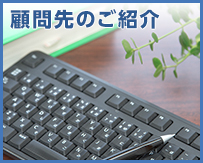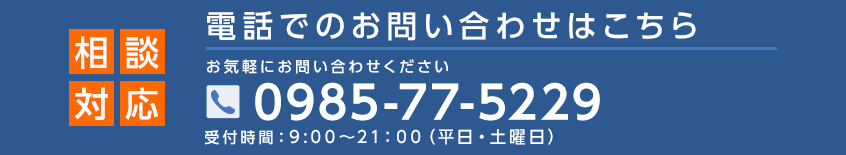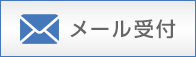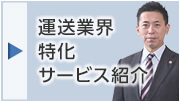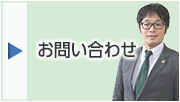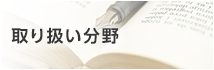債権回収を弁護士に依頼するメリットと判断基準について解説
今回は顧問先企業から相談を受けることが多いテーマ「債権回収」についてお話ししていこうと思います。
お話しする内容は以下のとおりです。
1 債権回収の重要性
2 債権回収を自社で対応するリスク
3 債権回収を弁護士に依頼するメリット
4 債権回収を弁護士に依頼するかどうかの判断基準
5 当事務所のサポート内容
それでは早速内容に入っていきましょう!
1.債権回収の重要性
企業活動において、商品やサービスの提供後に代金を回収する「債権回収」は、売上を「真の利益」に変える最終工程です。回収が滞れば、いくら売上があってもキャッシュフローが悪化し、運転資金が不足します。
特に中小企業にとって、売掛金の未収は経営に深刻な影響を及ぼし、最悪の場合、倒産のリスクさえ生じさせます。債権回収は、企業の健全な資金繰りを維持し、事業継続性を担保するための生命線と言えるでしょう。
2.債権回収を自社で対応するリスク
債権回収は、法律的な知識と適切な手続きの知識が求められる専門性の高い分野です。これを安易に自社の人員、特に法務担当ではない部署が行うことには、多くのリスクが伴います。
具体的には以下のとおりです。
①法的なリスクと限界
弁護士法72条に規定される非弁行為に抵触する恐れがあるほか、法律に基づかない強引な交渉は、後に違法な取り立てとして訴えられるリスクを負います。また、裁判所を通じた法的手続き(支払督促、訴訟、強制執行など)の知識や経験がないため、有効な手段が取れないことがほとんどです。
②時間的・心理的コスト
債権回収は、通常業務を圧迫する膨大な時間と労力を要します。また、債務者との直接的な交渉は、担当者に大きな心理的ストレスを与え、企業間の関係性が修復不可能なほど悪化する可能性もあります。
③回収率の低下
経験不足から、債務者の財産状況や誠意を見誤り、回収のタイミングを逃したり、不適切な和解に応じてしまったりすることで、本来回収できたはずの金額を取り逃がすことになりかねません。
④実務上よくある会社でのまずい対応
債権回収にあたって電話で請求をし、次に請求書を郵送またはFAX送信し、その次に郵送方法を書留に変えて、最後に内容証明郵便で郵送するといった順番で請求方法を変えていくという会社が多いと思います。
この対応が間違っているとは思いませんが、支払いの「催告」には暫定的な消滅時効の更新効(旧民法だと「中断効」)しかないとされていますので、「催告」方法をより確実な方法に変えていっても催告自体では消滅時効が更新されず最初の催告から6か月を超えても「催告」をしていると消滅時効期間が進行していくことになります(民法第150条第1項参照)。
ここで述べましたとおり、本来は最初の催告から6か月以内に民事訴訟を提起するなどして消滅時効の更新を確定的なものにする必要があるのにそれをご存じない会社が多いようです。
会社からの「催告」に応じて債務者が「支払います」という回答をくれれば当方の権利を「承認」したものとしてそこまでに進んだ消滅時効期間がリセットされます。
これが時効の更新であり、これを目的として請求書を郵送するなどの「催告」を行っているということであれば良いのですが、相手方から何の反応がない場合も漫然と請求書を送付し続けている会社を見ることは珍しくありません。
このような対応を続けていると最終的には消滅時効が完成してしまいますし、他の債権者がきちんとした対応で債権回収をしている間、債務者の資産状況は悪化し続けていくことも考えられますので貸し倒れリスクが徐々に高くなっていくことになります。消滅時効の完成の前に債務者からの回収が事実上不可能になったり法的に不可能になったりすること(取引先である債務者の破産によって)も考えられます。
3.債権回収を弁護士に依頼するメリット
弁護士に債権回収を依頼することで、これらのリスクを回避し、最大限の回収効果を目指すことができます。
メリットを表にまとめてみました。
|
メリット |
具体的な効果 |
|
法的手段の活用 |
内容証明郵便によるプレッシャーから、訴訟、債務名義をとった後の差押え(強制執行)に至るまで、全ての法的手続きを速やかに実行できます。特に、弁護士からの督促は、債務者に対して誠実に対応しないと「次は法的な措置に進む」**という強いメッセージとなり、その段階での回収可能性を高くします。 |
|
時間と労力の解放 |
企業は回収業務から解放され、コアビジネスに集中できます。債権回収を担当する部署、担当者の精神的な負担も軽減されます。 |
|
公正かつ専門的な交渉 |
弁護士が法律に基づき冷静に交渉を進めるため、感情的な対立を避け、債務者の財産状況等を正確に把握した上で、回収実現性の高い和解案を導き出すことができるケースも少なくありません。 |
|
時効の完成阻止 |
債権の消滅時効を完成させないよう、適切なタイミングで時効更新措置を講じることができます。 |
|
企業イメージの保護 |
弁護士が窓口となることで、企業自身が強硬な取り立てをしているという印象を避け、コンプライアンスを遵守した企業姿勢を保てます。 |
4.債権回収を弁護士に依頼するかどうかの判断基準
全ての債権回収を弁護士に依頼する必要はありませんが、以下の基準に照らして判断することをお勧めします。
① 金額の基準
回収額が弁護士費用を上回るか
まずは回収見込額が、弁護士に支払う着手金や報酬などの費用を上回るかどうかを計算します。回収額が数十万円以下の小口債権は、費用対効果を慎重に検討する必要があります。
ただ金額が少額でも将来的な取引に関わる場合、例えば少額でも、債務者に多くの債権者がいる場合(他の会社も同じ相手方に債権を持っている場合)には他の債権者に先んじてアクションを起こして回収しないと貸し倒れリスクが非常に高くなります。
他の債権者が回収できた中、自社だけが回収できなかったとなると現場の士気にも関わりますし、将来同様の場面でも同じ轍を踏まないように、費用対効果をある程度無視してでも回収する努力をした方が良い場面だと思います。
また、きちんとした回収をせずに売掛金の未収を確定させてしまうと、代金を支払わずにやり過ごせたという成功体験を債務者に与えることになり、そのような情報が他の取引先にも伝わると今後の債権回収にあたっての障害になる可能性があります。かかる事態を防ぐため、すなわち取引の「ケジメ」をつける必要がある場合は、弁護士への依頼が将来のトラブル防止に繋がります。
② 債務者の態度の基準
・連絡が取れない、無視している場合
債務者が事実上の逃亡状態にある、あるいは明確に支払いを拒否している場合は、話し合いでの解決は困難であり、法的手段が必須となります。
・支払いを口約束だけで延期し続けている場合
悪質な債務者ほど、口実を設けて時間を稼ごうとします。この場合、迅速に法的措置に移行しないと、債務者の財産が散逸してしまうリスクがあります。
③ 回収の緊急性の基準
・消滅時効の完成が迫っている場
債権の消滅時効が間近に迫っている場合、直ちに弁護士に依頼し、時効の更新措置を取る必要があります。それまでに催告を繰り返しているだけの場合には支払督促の申立てや民事訴訟の提起によって消滅時効を確定的に更新する必要があるのです。
・債務者が倒産しそうな情報がある場合
債務者が他の債権者から訴訟を受けている、手形・小切手の不渡りを出したなど、倒産の危険性がある場合は、他の債権者に先駆けて債権保全(仮差押えなど)を図るため、速やかな対応が必要です。
これらの基準を満たす場合は、躊躇せず専門家である弁護士にご相談ください。早めの行動こそが、債権回収の可能性を高めることになります。
5.当事務所のサポート内容
当事務所は多くの会社の顧問業務を日常的に行っており,その中で債権回収についての相談を受けるケースも少なくありません。
当事務所に限らず債権回収のスポットでの依頼でも着手金として25万円から30万円、それ以上の額をいただく法律事務所は少なくありません。
そうすると前述の費用対効果については債権が回収不能になるリスクも考えると弁護士にスポットで依頼しても割に合う請求額は少なくも100万円以上になると思います。
一方、100万円を切る債権回収について自社で裁判所を使った手続きをとると考えると、そこに担当者が割く時間や労力という目に見えないコストが発生することになり、少額の債権回収については法務部がない会社や債権回収にマンパワーを避けない会社では手詰まりになることも珍しくないと思います。
このような会社のニーズにもお応えするために当事務所では顧問先からの依頼でしたら100万円を切る債権回収、少ない場合だと数万円の債権回収についても実費だけご負担いただいて会社の代理人弁護士として内容証明郵便で通知書を送付して書面ベースでの交渉を行うといった対応をさせていただいております。その結果、売掛金を満額回収できるケースも珍しくありません。
また顧問先の依頼でスポットの依頼よりは割安で(顧問先向けの割引適用で)、債権回収のために支払督促の申立てや民事訴訟の提起を会社の代理人弁護士として行うこともございます。
債権回収についてお悩みの会社経営者、債権管理を担当されている部署の責任者は会社として当事務所との顧問契約を締結し、顧問業務の一環として債権回収を依頼されるのがお得なケースも少なくないと思います。
当事務所との顧問契約を検討されたい会社経営者の皆様,債権管理を担当されている部署の責任者の皆様は遠慮なくお問い合わせください。

文責 弁護士 濵田 諭
- 円満退職を叶える退職勧奨のポイント|企業法務に詳しい弁護士が解説
- 債権回収を弁護士に依頼するメリットと判断基準について解説
- 既に退職した社員から現場への直行直帰を伴う就労について現場への移動時間、現場からの戻り時間についても労働時間であり、この時間について賃金が支払われていないことを理由に未払い賃金を請求されたものの元社員の請求額を大幅に削った内容の判決から付加金を削った内容にて控訴審が判決を下し、これが確定して解決した事例
- 懲戒解雇とは?懲戒解雇が認められる場合、認められない場合について、弁護士が解説
- 【ご報告】代表弁護士柏田笙磨が国際ロータリー第2730地区の危機管理委員(弁護士)に選任されました
- 解雇の種類と注意すべきポイントを弁護士が解説
- 問題社員について解雇するのではなく交渉によって会社都合退職という形で合意退職による解決ができた事例
- 遅刻や欠勤を繰り返す問題社員を放置するリスクとは?企業が知っておくべき対応方法について弁護士が解説
- 業務の指示に従わない社員にどう対応する?問題社員対応について弁護士が解説
- 非違行為のある社員とは?企業の適切な対応方法について弁護士が解説