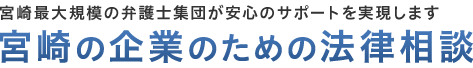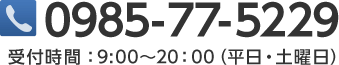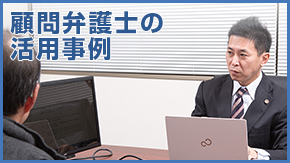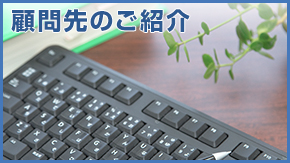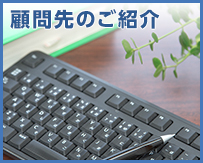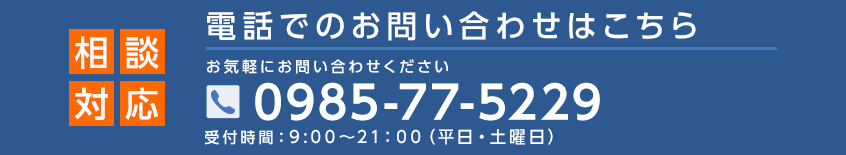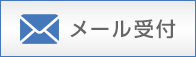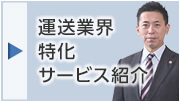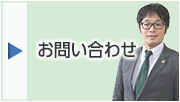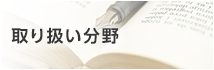業務の指示に従わない社員にどう対応する?問題社員対応について弁護士が解説
今回は顧問先や懇意にしている社労士の先生方からも良く相談される業務の指示に従わない社員への対応についてお話ししていこうと思います。
お話しする内容は以下のとおりです。
1 業務指示に従わない社員とは
2 業務指示に従わない社員が会社にもたらす悪影響
3 業務指示に従わない社員への対応方法
4 対応する際の注意点
5 問題社員対応に関して弁護士に相談するメリット
6 当事務所のサポート内容
それでは早速内容に入っていきましょう。
1.業務の指示に従わない社員とは
業務の指示に従わない社員とは、企業が正当な権限に基づき発する業務上の指示、命令、ルール等に対して、正当な理由なくこれに応じない、あるいは反抗する従業員を指します。具体的には、以下のような行動が挙げられます。
・指示された業務に着手しない、あるいは途中で放棄する
・指示された業務の内容を自己判断で変更する
・業務の報告・連絡・相談を怠る、あるいは虚偽の報告をする
・就業規則や会社のルール(服務規律、情報管理規定など)に違反する
・上司や同僚からの助言・指導を無視する、反発する
・職場の秩序を乱す言動を繰り返す
これらの行動は、単なる能力不足や理解不足とは異なり、社員の「指示に対する意図的な不履行」や「反抗的な態度」が根底にある場合に問題となります。労働契約は、労働者が使用者の指揮命令下で労務を提供することを内容とするものであり、使用者の業務命令に従うことは、労働契約上の労働者の基本的な義務です(民法第623条、労働契約法第3条第1項)。したがって、業務の指示に従わない行為は、この基本的な義務に違反するものであり、重大な規律違反となり得ます。
2.業務の指示に従わない社員が会社にもたらす悪影響
業務の指示に従わない社員は、単に個人の問題に留まらず、会社全体に深刻な悪影響をもたらします。
(1) 業務効率の低下と生産性の悪化
最も直接的な悪影響は、業務効率の低下と生産性の悪化です。指示された業務が適切に遂行されないため、プロジェクトの遅延、納期の厳守困難、品質の低下などが発生します。他の社員がその社員の未遂行分をカバーする必要が生じ、チーム全体の業務負担が増加し、残業時間の増加や士気の低下を招くこともあります。
(2) 職場の秩序とモラルの低下
業務の指示に従わない社員の存在は、職場の秩序を著しく乱します。正当な業務命令が無視される状況が常態化すれば、他の社員は「なぜ自分だけが指示に従うのか」という不公平感を抱き、真面目に業務に取り組む社員のモチベーションを低下させます。結果として、職場全体の規律が緩み、連鎖的に同様の行動を誘発する可能性もあります。
(3) 顧客からの信頼失墜と企業イメージの悪化
業務指示の不履行が原因で、顧客への対応が遅れたり、提供する商品やサービスの品質が低下したりすれば、顧客からの信頼を失い、企業のイメージを損ないます。これは長期的に見て、売上減少や新規顧客獲得の困難さにつながる可能性があります。
(4) 他の社員への悪影響と離職の誘発
業務の指示に従わない社員が放置されると、真面目に働く社員は不公平感や不満を募らせ、ストレスを抱えることになります。これが限界に達すると、優秀な社員が離職を選択する事態に発展する可能性もあります。人材流出は、企業の競争力低下に直結する深刻な問題です。
(5) 紛争リスクの増大
業務の指示に従わない社員に対し、会社が毅然とした対応を取らない場合、その行為がエスカレートし、ハラスメントやその他の問題行動に発展する可能性があります。また、最終的に解雇に至る場合には、不当解雇として争われるリスクも高まります。適切な対応を怠ることは、かえって法的紛争のリスクを高めることになります。
3.業務の指示に従わない社員への対応方法
業務の指示に従わない社員への対応は、事態の深刻度や社員の態度によって段階的に進める必要があります。
(1) 事実関係の確認と初期対応
まず、業務の指示に従わない状況が具体的にどのようなものであったか、事実関係を正確に把握することが重要です。
①具体的な指示内容の確認
どのような指示を、いつ、誰が、どのように行ったのか。
②不履行の具体的な状況
指示に従わなかったのはどの部分か、どのような結果が生じたか。
③社員の言い分
指示に従わなかった理由や背景について、本人の言い分を聴取する。
初期対応としては、まずは口頭で注意・指導を行い、指示に従うよう促します。この際、なぜその指示が必要なのか、指示に従わない場合にどのような影響があるのかを具体的に説明し、理解を促すことが重要です。
(2) 改善指導と業務命令書の交付
口頭での注意・指導にもかかわらず改善が見られない場合は、書面による改善指導や業務命令書を交付することを検討します。
①業務命令書
業務命令書には、具体的な指示内容、期限、従わない場合の会社の対応(懲戒処分の可能性など)を明記します。これにより、指示の明確化と、社員に状況の重大性を認識させる効果が期待できます。
②指導の記録
指導の内容、日時、社員の反応などを詳細に記録します。これは、後の懲戒処分や解雇の際に、会社が適切な指導を行ったことの証拠となります。
(3) 人事評価への反映
業務の指示に従わない行為は、社員の能力や貢献度を適正に評価する人事評価に反映されるべきです。不適切な人事評価は、社員のモチベーション低下につながるだけでなく、後の法的紛争において不当な評価であると主張される可能性もあります。
(4) 懲戒処分の検討と実施
①基本的な姿勢
度重なる注意・指導にもかかわらず改善が見られない場合や、業務の指示に従わない行為が重大な規律違反に該当する場合には、就業規則に基づき懲戒処分を検討します。懲戒処分の種類は、戒告、譴責、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇、懲戒解雇などがあり、違反行為の軽重に応じて選択します。
②就業規則の確認
懲戒処分の種類、事由、手続が就業規則に明確に定められていることを確認します。就業規則に規定のない懲戒処分はできません。
③適正手続の遵守
懲戒処分を行う際には、社員に弁明の機会を与えるなど、適正な手続を遵守する必要があります。
④証拠の確保
懲戒事由となる事実を裏付ける客観的な証拠(指示書、メール、記録、証言など)を十分に確保しておくことが不可欠です。
なお懲戒解雇の有効性が争われた事案では、裁判所の判断には、以下のような傾向があるといわれています。
・業務の指示や命令が不合理・不当なものでなければ,それに従わない行為は就業規則所定の懲戒解雇事由に形式的に該当するものの、その有効性が認められるためには、従わない行為が重大なものであって、企業秩序を現実に侵害したか又はその現実的な危険性を有することが必要であると考えている。
・手続的保障(就業規則所定の手続の履践、弁明の機会の付与等)を欠いていると相当性の要件を満たしていないと判断される傾向にある。
・労働者側に宥恕すべき事情がある場合には社会的相当性を欠いて無効と判断する傾向にある。
なお、懲戒解雇を有効と判断した裁判例としてボッシュ事件(東京地判平25・3・26労経速2179号14頁)などがあります。
(5) 退職勧奨・解雇の検討
①懲戒処分を行っても改善が見られない場合や、業務の指示に従わない行為が極めて悪質で、雇用関係の維持が困難と判断される場合には、退職勧奨や解雇を検討せざるを得ません。
退職勧奨: 会社が社員に対し自主的な退職を促すものです。合意によって雇用関係を終了させるため、後々の紛争リスクを低減できる可能性があります。しかし、あくまで「勧奨」であるため、社員が応じるかは任意です。
②解雇
業務指示に違反したことを理由とする懲戒解雇については、そのハードルが非常に高く、また懲戒解雇が有効な場合にも退職金の支給を全額免れるケースは稀なので懲戒解雇を選択すべきケースはほぼ皆無だと思います。
また普通解雇を選択する場合でも労働契約法第16条により、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」とされており、業務指示に違反したことによる解雇のハードルも非常に高いです。
会社からの業務指示を繰り返し無視しており、そのことによる業務への影響が甚大であること等の事情があることを立証できてようやく不当解雇と評価されない可能性が出てくるという話であり、普通解雇も避けるに越したことはありません。
ということで退職勧奨からの自主退職や合意退職に持ち込む方向での対応が最適解であることは間違いありません。
4.対応する際の注意点
業務の指示に従わない社員への対応は、一歩間違えれば不当解雇やハラスメントなどの法的紛争に発展するリスクを伴います。以下の点に細心の注意を払う必要があります。
(1) 就業規則の整備と周知
就業規則は、会社のルールであり、懲戒処分や解雇の根拠となります。業務命令違反に関する規定、懲戒事由、懲戒の種類、手続などが明確に定められ、社員に周知されていることが不可欠です。
(2) 客観的な証拠の収集と記録
口頭での指導や注意だけでなく、すべての指示、指導、面談の内容、日時、社員の反応などを書面で記録に残すことが極めて重要です。メール、業務日報、面談記録、注意指導書、業務命令書など、客観的な証拠を時系列で整理して保管します。これが後の法的紛争における会社の主張を裏付ける根拠となります。
(3) 段階的な対応と適正手続の遵守
いきなり重い懲戒処分や解雇を行うのではなく、まずは口頭注意から始め、改善が見られない場合に書面による指導、軽い懲戒処分と、段階的に対応を進めることが原則です。また、懲戒処分や解雇を行う際には、就業規則に定められた手続(弁明の機会の付与など)を厳格に遵守する必要があります。
(4) 公平性の確保
特定の社員に対してのみ厳しく対応したり、過去の同様の事例と比較して不公平な扱いをしたりすることは、不当な処分とみなされるリスクを高めます。常に公平な基準で対応し、社員間で不均衡が生じないよう注意が必要です。
(5) 周囲の社員への配慮
問題社員への対応は、他の真面目な社員の士気にも影響を与えます。問題社員の行動を放置せず、会社として適切な対応を取っていることを、間接的であっても示すことで、他の社員の不満を軽減し、信頼を維持することができます。ただし、具体的な対応内容をむやみに公開することは、プライバシー侵害や名誉毀損のリスクもあるため、慎重に行う必要があります。
(6) 専門家の意見を求めることの重要性
問題社員への対応は、労働法や判例の知識が不可欠であり、非常に専門的な判断が求められます。安易な対応は、予期せぬ法的紛争を招く可能性があります。特に、懲戒処分や解雇を検討する際には、必ず労働問題に詳しい弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けるべきです。
5.問題社員に関して弁護士に相談するメリット
業務の指示に従わない社員への対応は、企業の法的リスクを伴うため、弁護士に相談することには多くのメリットがあります。
(1) 法的なリスクの事前評価と回避
弁護士は、労働法や関連する判例・裁判例に基づき、会社が現在直面している問題社員への対応が法的に適切であるか、どのようなリスクがあるかを評価してくれます。これにより、不当解雇やハラスメントによる訴訟など、将来的な法的紛争のリスクを事前に回避するための助言を受けることができます。
(2) 適切な対応策のアドバイス
問題社員の状況や会社の就業規則、これまでの対応履歴などを踏まえ、最も適切でリスクの少ない対応策(指導方法、懲戒処分の種類、手続、退職勧奨の進め方など)について具体的なアドバイスを受けることができます。書面による指導書の作成支援や、面談時の注意点なども指導してもらえます。
(3) 証拠収集と保全のサポート
法的紛争になった際に有効な証拠をどのように収集し、保全すべきかについて、専門的な視点からアドバイスを得られます。これは、裁判になった場合に会社の主張を裏付ける上で不可欠です。
(4) 交渉の代理と代理人としての対応
問題社員との交渉(退職勧奨など)において、弁護士が代理人となることで、感情的な対立を避け、冷静かつ合理的な交渉を進めることができます。社員側が弁護士を立ててきた場合にも、対等な立場で交渉を進めることが可能になります。
(5) 紛争解決における代理人としての活動
万が一、問題社員が会社を提訴したり、労働審判を申し立てたりした場合、弁護士は会社の代理人として、法的手続きの準備、証拠の提出、主張の展開など、紛争解決のためのあらゆる活動を行います。これにより、会社は本業に専念しつつ、法的な問題を適切に処理することができます。
(6) 事例に即した戦略立案
弁護士は、過去の豊富な裁判例や実務経験に基づき、個別の事案に応じた最適な戦略を立案してくれます。これにより、杓子定規な対応ではなく、柔軟かつ効果的な問題解決を図ることができます。
6.当事務所のサポート内容
当事務所は既に裁判や労働審判に至っているケースにおける会社側の代理人としての対応、労働者側に代理人弁護士が付いている交渉における会社側の代理人としての対応をスポットで行うケースもありますが、基本的には会社と顧問契約を締結して顧問業務の範囲内で日常の問題社員対応に関する相談対応や懲戒処分の適用についての助言などを行い、不幸にして係争に発展した場合も顧問弁護士として引き続き会社側の代理人弁護士として対応していくことにしております。
労使紛争に発展しているケースにおいても既に発生している労使紛争の解決にとどまらず労使紛争に至った原因を除去して今後の紛争を予防する必要がありますので、紛争状態にある会社と顧問契約を締結してその業務として労使紛争における会社側の代理人として対応をするケースが多いです。
紛争の解決と今後の紛争予防に向けた取り組みを並行して行っていくイメージです。
労使紛争に既に巻き込まれており対応に苦慮されている会社経営者の皆様、問題社員対応に苦慮されており日常的に弁護士へ相談することで悩みを1人で抱え続ける精神的な負担を軽減したいとお考えの経営者、人事担当者の皆様、当事務所との顧問契約の締結をご検討されることをお勧めいたします。

文責 弁護士 浜田 諭
- 退職代行を使われたらどうする?対応のポイントについて弁護士が解説
- 円満退職を叶える退職勧奨のポイント|企業法務に詳しい弁護士が解説
- 債権回収を弁護士に依頼するメリットと判断基準について解説
- 既に退職した社員から現場への直行直帰を伴う就労について現場への移動時間、現場からの戻り時間についても労働時間であり、この時間について賃金が支払われていないことを理由に未払い賃金を請求されたものの元社員の請求額を大幅に削った内容の判決から付加金を削った内容にて控訴審が判決を下し、これが確定して解決した事例
- 懲戒解雇とは?懲戒解雇が認められる場合、認められない場合について、弁護士が解説
- 【ご報告】代表弁護士柏田笙磨が国際ロータリー第2730地区の危機管理委員(弁護士)に選任されました
- 解雇の種類と注意すべきポイントを弁護士が解説
- 問題社員について解雇するのではなく交渉によって会社都合退職という形で合意退職による解決ができた事例
- 遅刻や欠勤を繰り返す問題社員を放置するリスクとは?企業が知っておくべき対応方法について弁護士が解説
- 業務の指示に従わない社員にどう対応する?問題社員対応について弁護士が解説