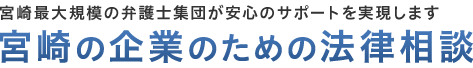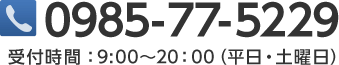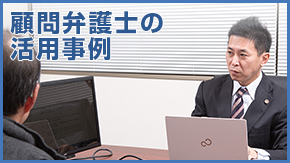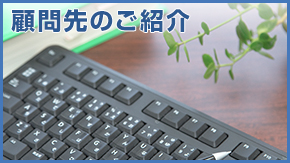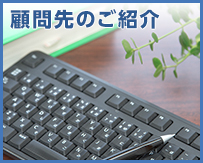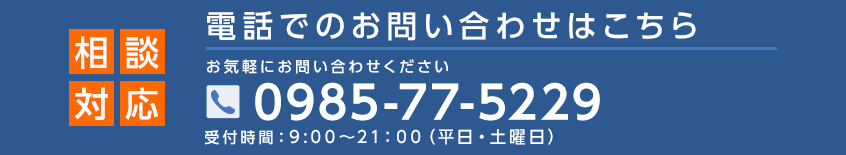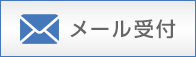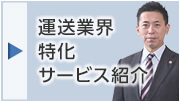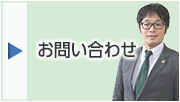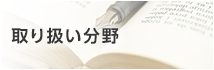円満退職を叶える退職勧奨のポイント|企業法務に詳しい弁護士が解説
今回は顧問先企業から相談を受けることが多いテーマ「退職勧奨」についてお話ししていこうと思います。
お話しする内容は以下のとおりです。
1 解雇と退職勧奨の違い
2 解雇を避けるべき理由
3 円満に退職してもらうための退職勧奨の進め方
4 退職勧奨が違法と評価されないためのポイント
5 退職合意書等の作成のポイント
6 退職勧奨に関して弁護士に相談するメリット
7 当事務所のサポート内容
1 解雇と退職勧奨の違い
解雇とは、会社(使用者)側から一方的に雇用契約を終了させることです。日本の労働法では、解雇は厳しく制限されています。
退職勧奨は、会社が社員に対して退職を「勧め」、社員の自由な意思による退職の合意を目指すことです 。これは、あくまで話し合いであり、社員が応じるかどうかは自由です 。退職勧奨が成功し、社員が退職に同意すれば「合意退職」となります 。
2 解雇を避けるべき理由
会社が社員を解雇するのではなく、退職勧奨による合意退職で処理すべき理由は、主に以下の3点です 。
(1)解雇の有効性が認められるケースが少ない
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、権利の濫用として無効とされます(労働契約法16条) 。
能力不足を理由とする解雇は、有効と認められるケースはまれです 。
ハラスメントを理由とする解雇も、その程度や頻度が著しい場合以外では不当解雇とされる傾向が強いです 。パワハラで暴力を伴わないケースだと有効になるケースは少ないです 。
(2)紛争が長期化し、裁判で敗訴した場合の損害が大きい
不当解雇と判断された場合、会社は大きな損害を被るリスクがあります 。
①バックペイ(さかのぼって賃金支払い)の必要
解雇が無効になると、解雇から判決までの雇用契約が存続していたと評価され、会社は期間中の賃金を支払う必要があります 。
②職場復帰の必要
社員の職場復帰を認めなければならない事態が生じ、事業所に混乱が生じます 。
③多額の解決金の支払い
職場復帰を認めない和解をしようとする場合、多額の解決金を支払わなければならないケースが多いです 。一度不当解雇と裁判所に判断された後(一審での判決が出た後)の控訴審での和解は、バックペイに加えて1年以上の賃金相当額の解決金の支払いが必要になることも珍しくありません。
(3)裁判になった場合の費用と労力の大きさ
裁判になると、弁護士費用だけでなく、総務担当者などが弁護士との打ち合わせや書面確認に労力と時間を取られるなど、紛争解決という後ろ向きの作業に多大な労力と時間を費やすという不合理性があります 。
3 円満に退職してもらうための退職勧奨の進め方
円満な合意退職を叶えるためには、以下のフローで慎重に進める必要があります 。
(1)退職勧奨の方針決定と情報共有
退職社員の方針を決定し、役員・総務担当者と共有します 。
退職勧奨が成功した場合の人員確保などについても情報共有が必要です 。
(2)理由の整理(手控えの作成)
ハラスメント、能力の問題、協調性不足など、会社としてその社員が必要でないことを裏付ける事実を社内で収集し、文書化します(手控え) 。
これは、社員に退職を伝える際の根拠となります 。
(3)予算の確保
退職したくない社員を説得する材料として、金銭支払いの提示という手段があるため、退職金や解決金の支払原資を確保します 。
いつまでにいくら支払えるかなど、予算の検討と確保は必須です 。
(4)想定シミュレーションの実施
社員と話す際に誤った対応をしないよう、また、頭が真っ白になる事態を避けるために、想定される質問への回答を準備し、シナリオを作成します 。
想定される質問と回答例は以下のとおりです。
Q: 「これって解雇ですよね?」 → A: 「違います。あくまでも退職に向けた話し合いです。」
Q: 「これに応じなかったらどうなるんですか?」 → A: 「現時点では解雇することは考えていません。今後の話し合いによって合意による解決ができればと考えています。」
Q: 「次の就職先が決まるまでは、会社にいさせてください。」 → A: 「希望としては伺いますが、不確定な時期までの在職を認めるという対応はしかねます。」
(5)社員を個室に呼び出す
他の社員の目に触れない、会社の会議室などの個室に呼び出します 。
会社側は2名くらいまでが妥当です。3名を超えると、圧迫的な退職勧奨をされたとの社員側の主張を許す可能性が高くなります(2対1、または1対1が穏当) 。
(6)退職して欲しいという会社の希望を伝える
退職勧奨ですので、退職してほしいという希望は明確に伝えなくてはいけません。
それは大前提としてどのような話をしていくべきかをお伝えします。
①それまでの社員の評価と課題、会社として与えてきた成長・改善の機会を伝える。
②現在の社員の状態と、会社としてこれ以上の成長・改善が見込めないと判断していることを伝える 。
③会社としては社員に退職して欲しいと考えていると伝える 。なお社員からの反論には手控えを利用して対応します 。
④退職勧奨について終わりが見えない交渉になることを避けるために退職勧奨に対する社員側の回答期限を伝えます 。
⑤退職勧奨時に社員が条件次第で退職する態度の場合には希望条件を聞き、会社が用意した条件を超える場合はその場で判断せず、次の機会を設定して検討結果を伝えます 。
(7)退職届を提出させる
退職勧奨を踏まえて(何度かの退職勧奨の後に合意に至るケースが多いですが)条件面で合意ができれば退職届を提出させます 。
退職届には「一身上の都合により」ではなく、「会社からの退職勧奨を承諾し、令和○年○月○日付で退職します」と記載させます 。その場で日付と署名・捺印が取れれば最善ですが、無理をしてはいけません。
(8)退職合意書の作成
退職に向けての条件面を双方が合意した旨の退職合意書を作成します 。
通常は2通を作成して、双方が1通ずつ保管します 。
4 退職勧奨が違法と評価されないためのポイント
「執拗な」退職勧奨には違法な「退職強要」と評価されるリスクがあり、その場合、退職の意思表示が無効(雇用契約継続、バックペイ+職場復帰または多額の解決金)となったり、慰謝料の支払義務が生じたりします 。
(1)「執拗な」退職勧奨を避ける
回数・時間:1回あたり30分程度、7回の退職勧奨を適法と評価した裁判例があります(サニーヘルス事件 東京地裁平成22年12月27日判決) 。
明確に退職を拒否している社員に対して、同じ態様の退職勧奨を行うと「執拗」「違法」と評価されるリスクがあります 。
(2)やってはいけないこと(具体例)
以下の行為は違法と評価され、慰謝料の支払いにつながる可能性があります。一般的にパワハラと評価される言動は退職勧奨時も避けるべきです 。
①発言上の注意点
職務能力の評価は仕方ないとしても、人格批判に及ぶ発言は違法と評価されると考えた方が良いです 。
②情報共有の注意点
対象者以外への働きかけや、対象者以外にも広く情報共有されているかのような発言は避けるべきです 。対象社員の両親や配偶者に説得を依頼するといった行為や退職勧奨についての情報が社内で広く共有されていることをほのめかす発言は避けるのが無難です。
(3)退職勧奨時のタブー
以下の発言は、退職合意が無効になったり、不当解雇と同じ結果になるリスクがあります 。
①「退職しない場合には解雇する」との発言
不当解雇と同じ結果になり、バックペイ+職場復帰(又は多額の解決金の支払い)となるリスクがあります 。
②懲戒解雇の予告、刑事告訴とバーターにすること
「横領だから責任をとれ。告訴や懲戒解雇だと困るだろう」→「強迫」に基づく退職の意思表示とみなされ、取り消しが認められるリスクがあります 。
③「懲戒解雇を避けたくないのか」「自主退職であれば退職金は出る」「懲戒解雇の場合には退職金は支払わない」
退職の意思表示が無効とされ、多額のバックペイ支払いと雇用の継続を命じられた判決例があります 。
④懲戒解雇も検討している案件での勧奨方法の一案を示します。
「懲戒事由がある」「懲戒解雇を含む厳重な処分を下す可能性がある」「今後、懲戒処分に向けて事実確認について協力していただく必要がある」と告げる 。
ここで一度区切って、「なお、あなたが退職される場合には受け入れる準備がある」と伝えると、これで違法と評価されるリスクは軽減できると考えられます 。
(4)退職を目的とした配置転換や仕事の取り上げ
本人の経歴にそぐわない不適切な職への配置転換、仕事を取り上げるなどは、それ単体でパワハラと評価され、慰謝料の発生原因にもなります 。
退職勧奨中に1人の部屋(通称「追い出し部屋」)で執務させ、他の社員との関係を遮断した事案では、150万円の慰謝料支払いが命じられました(大和証券ほか1社事件 大阪地方裁判所平成27年4月24日判決) 。
ミスの多い社員や他の社員との軋轢が生じている社員を別の部署に配転すること自体は問題ありませんが、なぜ配転するのかをきちんと社員に説明する必要があります 。
なお、その社員について職種限定雇用の場合は、その職種以外への配転は不可であるため注意が必要です 。
5 退職合意書等の作成のポイント
退職合意書には、労働者から退職合意を引き出す要素として、主に以下の点を記載します 。
(1)退職勧奨による離職とする
離職理由を「退職勧奨」とすることで、社員の失業給付受給の便宜を図ります 。
この際の注意点を述べます。
雇用関係の助成金(例:中途採用拡大コース、トライアル雇用助成金)を利用している場合、受給権を失う、または金額が減らされるリスクがあるため、事前確認が必要です 。
(2)退職金や解決金の支給
支給の考え方については以下のとおりです。
退職金支給規定があり要件を満たすなら、それだけで終わらせるのが基本です 。
支給規定がない、または要件を満たさない場合は、支給しないのがスタートラインです 。
提示額を下げることは難しいため、低いところからスタートします(例:10万円→賃金1か月分→2か月分→3か月分) 。
退職金・解決金の相場観についてですが、現在の実務上、社員に退職意思が少しでもある場合は賃金3か月以内相当の退職金・解決金で解決できる印象です 。
もし賃金3か月分を超える金銭を支払う場合は、その社員が会社にもたらす不利益(周りの社員の離職リスクなど)を回避するために金員を払う費用対効果の検証が必要です 。
なお合意書への記載について、退職金、解決金名目であっても源泉徴収が必要なため、その点を明記し、支払う場合の送金先口座も明確にしておきます 。賃金の送金先口座と同じであればその旨を合意書に記載します。
(3)退職時期
賞与支給後の退職にすれば同意が得られる可能性が高くなります 。
ただし、社員の在職が会社にもたらすリスクが高い場合は、時期を遅らせるべきではなく、退職金・解決金の上乗せを検討した方が良いです 。
合意書で、出勤がいつまでで、いつから有給消化なのかを明確にしておきます 。
(4)清算条項
退職合意書の最後の条項で本合意書に定める外、当事者間には何らの債権債務がないことを相互に確認するという清算条項を入れるのが通常ですが、この条項については以下の点をご注意下さい。
「本件に関し」などの清算範囲を限定する文言は付けないようにします 。清算範囲を限定しない清算条項を包括的清算条項といいますが、この条項を入れることで在職中の未払い賃金請求権(残業代等)も消えることになります 。
6.退職勧奨について弁護士に相談するメリット
退職勧奨の具体的な進め方や注意点を聞きながら対象者である社員の対応に応じて適宜適切な対応をすることが可能になります。違法な退職勧奨を行うリスクを軽減し、交渉を有利に進めるための助言を得ながら進めることで合意退職による円満解決に向かう可能性が高くなります。
7.当事務所のサポート内容
当事務所は多くの会社の顧問業務を日常的に行っており,その中で退職勧奨についての相談を受けるケースも少なくありません。また退職勧奨、解雇に限らず顧問業務の中で問題社員との雇用契約終了に向けてのアドバイス,退職勧奨の方法等についての助言、雇用契約終了について紛争化した場合の会社の代理人としての交渉対応,訴訟対応などを行っております。
社員との雇用契約終了(解雇,退職等)に向けて弁護士から適切な助言を得るには,紛争化した後のスポットでの対応を依頼するよりも,日頃から問題社員対応について弁護士から助言を得られる体制作りをされること(顧問弁護士を依頼されること),顧問弁護士に問題社員対応等を相談することを習慣にされることをお勧めします。このことにより会社の業務や社内での人間関係を理解した上での助言を顧問弁護士から得ることが可能となるからです。
当事務所との顧問契約を検討されたい会社経営者の皆様,人事担当者の皆様は遠慮なくお問い合わせください。
- 円満退職を叶える退職勧奨のポイント|企業法務に詳しい弁護士が解説
- 債権回収を弁護士に依頼するメリットと判断基準について解説
- 既に退職した社員から現場への直行直帰を伴う就労について現場への移動時間、現場からの戻り時間についても労働時間であり、この時間について賃金が支払われていないことを理由に未払い賃金を請求されたものの元社員の請求額を大幅に削った内容の判決から付加金を削った内容にて控訴審が判決を下し、これが確定して解決した事例
- 懲戒解雇とは?懲戒解雇が認められる場合、認められない場合について、弁護士が解説
- 【ご報告】代表弁護士柏田笙磨が国際ロータリー第2730地区の危機管理委員(弁護士)に選任されました
- 解雇の種類と注意すべきポイントを弁護士が解説
- 問題社員について解雇するのではなく交渉によって会社都合退職という形で合意退職による解決ができた事例
- 遅刻や欠勤を繰り返す問題社員を放置するリスクとは?企業が知っておくべき対応方法について弁護士が解説
- 業務の指示に従わない社員にどう対応する?問題社員対応について弁護士が解説
- 非違行為のある社員とは?企業の適切な対応方法について弁護士が解説