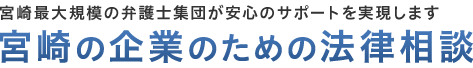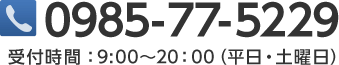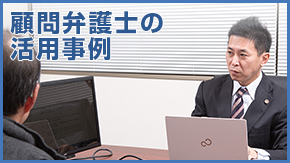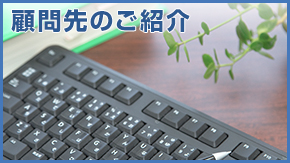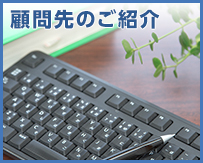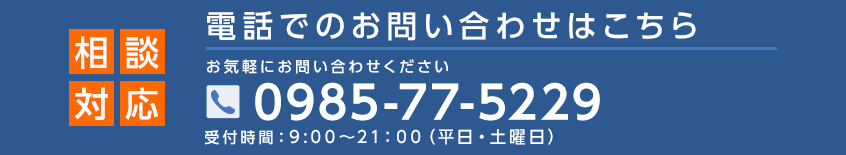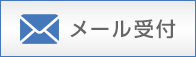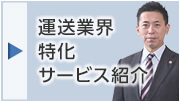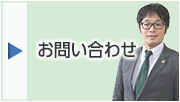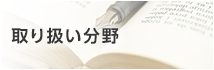非違行為のある社員とは?企業の適切な対応方法について弁護士が解説
今回は顧問先からも良く相談される非違行為のある社員への対応についてお話ししていこうと思います。
お話しする内容は以下のとおりです。
1 従業員の非違行為とは
(1)就業中の非違行為
①交通費、手当の不正受給
②接待交際費を私的に流用
③業務上横領
④備品の持ち帰り
⑤タイムカードの不正打刻
(2)私生活における非違行為
①職場外で、窃盗罪で逮捕される
②職場外で逮捕されたが容疑を否認している
③飲酒運転による事故を起こした
④不貞行為をしている
⑤反社会的勢力の構成員であることが判明した。
2 従業員の非違行為が会社に与える影響
3 非違行為を行った社員への対処法
4 非違行為を事前に予防するためのポイント
5 当事務所のサポート内容
それでは早速内容に入っていきましょう!
1.従業員の非違行為とは
従業員の非違行為とは、企業に所属する従業員が、就業規則や法令、社会通念に反する不正な行為を行うことを指します。これらの行為は、企業秩序を乱し、企業の信頼を損なうだけでなく、経済的な損失や法的責任を招く可能性もあります。従業員の非違行為は、大きく分けて就業中に行われるものと、私生活において行われるものに分類できます。
(1)就業中の非違行為
就業中に行われる非違行為は、職務遂行に関連する不正行為であり、企業の業務運営に直接的な悪影響を及ぼします。
① 交通費、手当の不正受給
交通費や各種手当は、従業員の通勤や業務遂行にかかる費用を補填する目的で支給されます。これを不正に受給する行為は、実際には発生していない費用を請求したり、過大な金額を申請したりするものです。例えば、実際よりも遠い経路で申請する、自家用車通勤であるにもかかわらず公共交通機関の料金を請求する、業務に必要な手当を私的な目的で使用するなどといったケースが考えられます。これは、会社の財産を不正に取得する行為であり、背任罪や詐欺罪に該当する可能性もあります。
② 接待交際費を私的に流用
接待交際費は、取引先との円滑な関係を構築するために必要な費用ですが、これを私的な飲食や遊興費に流用する行為は、会社の資金を不正に使用するものです。領収書を偽造したり、架空の接待をでっち上げたりするなどの手口が用いられることがあります。これも業務上横領罪に該当する可能性があり、会社の信頼を大きく損なう行為です。
③ 業務上横領
業務上横領は、会社から預託された金銭や物品を、自分のものとして不法に処分または領得する行為です。経理担当者が会社の資金を着服したり、営業担当者が売上金を担当者の個人口座に入金したりするケースが該当します。これは、10年以下の拘禁刑が科される可能性のある刑法上の重罪であり(刑法253条)、会社の存続を揺るがす深刻な事態を招きかねません。
④ 備品の持ち帰り
会社の備品は、業務遂行のために用意されたものであり、従業員が私的に使用したり、自宅に持ち帰ったりすることは原則として許されません。文房具や消耗品程度の持ち帰りであっても、それが常態化すれば会社の損失につながります。パソコンや機密情報を含む書類などを無断で持ち帰る行為は、情報漏洩のリスクを高めるだけでなく、窃盗罪(刑法235条)に該当する可能性もあります。
⑤ タイムカードの不正打刻
タイムカードは、従業員の労働時間を管理し、給与計算の基礎となる重要な記録です。本人以外の従業員に打刻を依頼したり、実際よりも長く労働時間を記録したりする不正打刻は、会社に対する詐欺行為であり、不当な給与を受け取るものです。これは、他の従業員の士気を低下させるだけでなく、会社の労務管理体制の信頼性を損なう行為です。
(2)私生活における非違行為
私生活における非違行為は、原則として従業員のプライベートな領域に関わるものですが、その内容によっては企業の信用や秩序に悪影響を及ぼす可能性があります。
① 職場外で、窃盗罪で逮捕される
従業員が職場外で窃盗罪を犯し逮捕された場合、その事実が報道などによって公になることで、企業のイメージが大きく損なわれる可能性があります。顧客や取引先からの信頼を失い、事業活動に支障をきたすことも考えられます。また、逮捕という事実は、従業員としての信用を失墜させるものであり、服務規律違反に該当する可能性があります。
② 職場外で逮捕されたが容疑を否認している
職場外で逮捕されたものの、従業員が容疑を否認している場合、事実関係が確定するまでは慎重な対応が求められます。しかし、逮捕されたという事実自体が企業の信用を傷つける可能性は否定できません。企業としては、事実関係の確認を進めつつ、従業員の弁明を聞くなどの適切な対応をとる必要があります。
③ 飲酒運転による事故を起こした
飲酒運転は、重大な犯罪行為であり、人命に関わる危険な行為です。従業員が飲酒運転で事故を起こした場合、企業の社会的責任が問われ、厳しい批判を受けることは避けられません。企業のイメージダウンは甚大であり、事業継続にも影響が出かねません。また、従業員自身も法的な処罰を受けることになります。
④ 不貞行為をしている
従業員の不貞行為は、原則として私的な問題であり、企業が直接的に関与することは難しいと考えられます。しかし、不貞行為が訴訟に発展し、その過程で従業員の所属する企業名が公になるような場合、企業のイメージが損なわれる可能性も否定できません。特に、倫理観が重視される業界や職種においては、影響が大きくなることもあります。また不貞行為の相手方やその配偶者が企業に押しかけてくるというトラブルが発生することもあり、こうなると企業の業務に支障を来すことになります。
⑤ 反社会的勢力の構成員であることが判明した
従業員が反社会的勢力の構成員であることが判明した場合、企業は直ちにその従業員との関係を断つ必要があります。反社会的勢力との関わりは、企業の健全な事業活動を阻害し、社会的な信用を失墜させるだけでなく、法令違反となる可能性もあります。企業は、平時から従業員の背景調査を徹底するなど、反社会的勢力との関係を遮断するための措置を講じる必要があります。
2.従業員の非違行為が会社に与える影響
従業員の非違行為は、会社に多岐にわたる悪影響を及ぼします。その影響は、経済的な損失に留まらず、組織全体の信頼や士気にまで及ぶ可能性があります。
(1)経済的な損失:
①直接的な損害: 横領や不正受給などによる会社の資金の損失、備品の紛失や破損による損害などが発生します。
②間接的な損害: 顧客や取引先からの信頼失墜による取引の減少、訴訟費用や損害賠償金の支払い、風評被害による株価の下落などが考えられます。
③調査費・対応費: 非違行為の発覚後の事実調査、弁護士費用、再発防止策の策定・実施にかかる費用などが発生します。
(2)組織への影響:
①企業イメージの低下: 顧客、取引先、株主からの信頼を失い、企業イメージが大きく損なわれる可能性があります。採用活動にも悪影響を及ぼすことがあります。
②従業員の士気低下: 他の従業員は、不正を行った従業員やそれを見過ごした会社に対して不信感を抱き、モチベーションの低下や離職につながる可能性があります。
③組織文化の悪化: 公正さや倫理観が損なわれ、組織全体のモラルが低下する可能性があります。不正行為が蔓延しやすい風土が形成されるリスクもあります。
④業務効率の低下: 調査や対応に人員や時間を割かれることで、本来の業務に支障が生じ、生産性の低下につながります。
⑤管理体制の不備露呈: 非違行為が発生したことは、内部統制やコンプライアンス体制の不備を示すものであり、改善の必要に迫られます。
⑥法的なリスク:
(1)民事上の責任: 被害者や関係者から損害賠償請求を受ける可能性があります。
(2)刑事責任: 非違行為の内容によっては、役員や従業員が逮捕・起訴される可能性があります。
(3)行政処分: 業種によっては、監督官庁から業務改善命令や営業停止などの行政処分を受ける可能性があります。
3.非違行為を行った社員への対処法
従業員が非違行為を行った場合、企業は事実関係を正確に把握し、公正かつ適切な対応をとる必要があります。感情的な対応ではなく、就業規則や関連法規に基づいた冷静な判断が求められます。
(1)初期対応
①事実確認: まずは、非違行為に関する情報を収集し、関係者からの聞き取りや証拠の保全を行い、事実関係を正確に把握します。
②調査委員会の設置: 必要に応じて、社内外の専門家を含む調査委員会を設置し、客観的な調査を行います。
③弁護士への相談: 法的な判断や今後の対応について、弁護士に相談し、適切なアドバイスを得ます。
④関係部署との連携: 人事部、法務部、監査部など、関連する部署と連携し、情報共有と協力体制を構築します。
(2)処分・措置
①就業規則の確認: 当該非違行為に対する就業規則の懲戒規定を確認します。
②懲戒処分の検討: 事実関係、非違行為の悪質性、会社に与えた影響などを総合的に考慮し、適切な懲戒処分を検討します。懲戒処分には、戒告、譴責、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇、懲戒解雇などがあります。非違行為の内容や頻度等によって適切な懲戒処分を選択して処分することが重要です。
③本人への弁明機会の付与: 懲戒処分を行う前に、本人に弁明の機会を与え、十分な説明を聞くことが重要です。
④懲戒処分の決定と通知: 決定した懲戒処分を本人に書面で通知します。理由や根拠、不服申し立ての方法なども明記します。
⑤刑事告訴・被害届の提出: 悪質な非違行為については、警察への刑事告訴や被害届の提出を検討します。
⑥民事責任の追及(損害賠償請求等): 会社に損害が発生している場合は、当該従業員に対して損害賠償を請求することを検討します。
⑦再発防止策の策定と実施: 今回の非違行為の原因を分析し、二度と繰り返されないよう、内部統制の強化や研修の実施などの再発防止策を策定し、実行します。
⑧関係者への説明と謝罪: 必要に応じて、顧客、取引先、株主などの関係者に対して、事実関係を説明し、謝罪を行います。
(3)留意点
①公平性の確保: 懲戒処分は、他の同様の事案とのバランスを考慮し、公平に行う必要があります。
②プライバシーへの配慮: 従業員のプライバシーに配慮し、不必要な情報公開は避けるべきです。
③感情的な対応の抑制: 感情的な判断ではなく、客観的な事実に基づいて対応することが重要です。
④記録の保管: 調査の過程や決定した処分に関する記録は、適切に保管する必要があります。
4.非違行為を事前に予防するためのポイント
従業員の非違行為を未然に防ぐためには、組織全体で意識を高め、適切な対策を講じることが重要です。具体的には以下のとおりです。
(1)組織文化の醸成
①倫理観の重視: 企業理念や行動規範において、倫理観の重要性を明確に示し、従業員に浸透させます。
②コンプライアンス意識の向上: 定期的な研修や啓発活動を通じて、法令遵守の意識を高めます。
③オープンなコミュニケーション: 風通しの良い職場環境を作り、従業員が問題や不正行為について報告しやすい雰囲気を作ります。
④ハラスメントの防止: パワーハラスメントやセクシュアルハラスメントなどの不正行為の温床となるハラスメントを防止するための取り組みを徹底します。
⑤ワークライフバランスの推進: 従業員のストレス軽減や心身の健康維持に配慮し、不正行為に走る要因を減らします。
(2)内部統制の強化
①職務分掌の明確化: 業務における責任と権限を明確にし、牽制機能を働かせます。
②承認プロセスの厳格化: 重要な取引や支出については、複数による承認を義務付けるなど、チェック体制を強化します。
③定期的な内部監査: 内部監査部門による定期的な監査を実施し、不正リスクを早期に発見します。
④内部通報制度の整備: 従業員が不正行為を匿名で通報できる窓口を設置し、適切な運用を行います。通報者保護を徹底することも重要です。
⑤ITシステムの活用: 証拠が残るようなシステムを導入し、不正行為を抑止します。アクセスログの監視なども有効です。
⑥入社時の身元調査: 採用時に、過去の犯罪歴や反社会的勢力との関わりがないかなど、適切な身元調査を実施します。中小企業では中々実施するのが難しいと思います。
⑦教育・研修の実施:
ア 新入社員研修: 入社時に、企業の倫理観やコンプライアンスに関する基本的な知識を教育
します。
イ 階層別研修: 管理職に対しては、不正行為の兆候を早期に発見するための知識や、部下が
不正行為を行った場合の適切な対応について研修を行います。
ウ テーマ別研修: 不正受給、横領、情報漏洩など、具体的な非違行為の事例やリスク、予防
策について研修を行います。
エ eラーニングの活用: 時間や場所にとらわれずに学習できるeラーニングを活用し、継続
的な教育を実施します。
(3)その他
①就業規則の明確化と周知: 就業規則において、禁止事項や懲戒処分の内容を具体的に定め、全従業員に周知徹底します。
②経営層の姿勢: 経営層自身が倫理的な行動を模範とし、コンプライアンスを重視する姿勢を示すことが、従業員の意識向上につながります。
③外部専門家との連携: 必要に応じて、弁護士や社会保険労務士などの外部専門家と連携し、適切なアドバイスやサポートを得ます。
これらの予防策を講じることで、従業員の非違行為のリスクを低減し、健全な企業運営と信頼性の向上を図ることができます。非違行為は、企業にとって大きな損失をもたらす可能性があるため、予防に重点を置いた取り組みが不可欠と言えるでしょう。
5 当事務所のサポート内容
当事務所は多くの会社の顧問業務を日常的に行っており、顧問業務の中で従業員の非違行為を受けた対応についての助言、紛争化した場合の会社の代理人としての交渉対応、訴訟対応、非違行為防止のための対策の助言などを行っております。
社員の非違行為への対応、紛争化した場合の対応、再発防止への取組みなどを総合的に
対処するためには被害が生じた場合のスポットでの対応よりも常日頃からの会社の業務や
社内での人間関係を理解した上での対応が可能な顧問業務を弁護士に依頼されることをお勧めします。
当事務所との顧問契約を検討されたい会社経営者の皆様,人事担当者の皆様は遠慮なくお問い合わせください。
- 退職代行を使われたらどうする?対応のポイントについて弁護士が解説
- 円満退職を叶える退職勧奨のポイント|企業法務に詳しい弁護士が解説
- 債権回収を弁護士に依頼するメリットと判断基準について解説
- 既に退職した社員から現場への直行直帰を伴う就労について現場への移動時間、現場からの戻り時間についても労働時間であり、この時間について賃金が支払われていないことを理由に未払い賃金を請求されたものの元社員の請求額を大幅に削った内容の判決から付加金を削った内容にて控訴審が判決を下し、これが確定して解決した事例
- 懲戒解雇とは?懲戒解雇が認められる場合、認められない場合について、弁護士が解説
- 【ご報告】代表弁護士柏田笙磨が国際ロータリー第2730地区の危機管理委員(弁護士)に選任されました
- 解雇の種類と注意すべきポイントを弁護士が解説
- 問題社員について解雇するのではなく交渉によって会社都合退職という形で合意退職による解決ができた事例
- 遅刻や欠勤を繰り返す問題社員を放置するリスクとは?企業が知っておくべき対応方法について弁護士が解説
- 業務の指示に従わない社員にどう対応する?問題社員対応について弁護士が解説