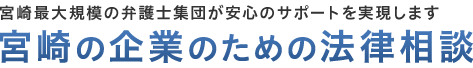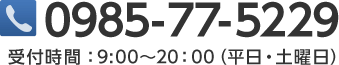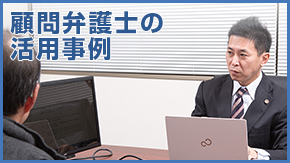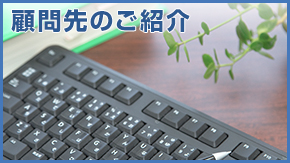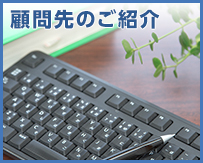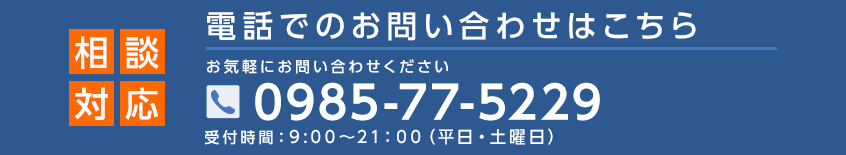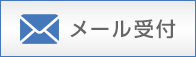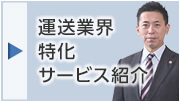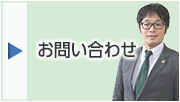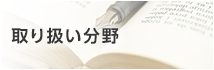遅刻や欠勤を繰り返す問題社員を放置するリスクとは?企業が知っておくべき対応方法について弁護士が解説
今回は顧問先や懇意にしている社労士の先生方からも良く相談される業務の指示に従わない社員への対応についてお話ししていこうと思います。
特に、遅刻や欠勤を繰り返す社員への対応は、多くの企業にとって頭の痛い問題です。真面目に働く社員のモチベーションを低下させ、組織全体の生産性を著しく損なうだけでなく、放置すればするほど、後々大きな法的トラブルに発展する可能性も秘めています。
本稿では、この問題に直面した企業の人事担当者や経営者の皆様が、適切な手続きを踏んで対応を進めることができるよう、具体的なステップと注意点、そして専門家への相談の重要性について詳しく解説していきます。
お話しする内容は以下のとおりです。
1 遅刻や欠勤を繰り返す問題社員を放置するリスク
2 遅刻や欠勤を繰り返す問題社員への対応方法
3 対応する際の注意点
4 問題社員対応に関して弁護士に相談するメリット
5 当事務所のサポート内容
それでは早速内容に入っていきましょう。
1. 遅刻や欠勤を繰り返す問題社員を放置するリスク
「そのうち改善するだろう」「厳しく注意して辞められても困る」といった理由で、勤怠不良の社員を放置することは、会社にとって計り知れないリスクを招きます。
(1)組織全体の士気低下とモラルハザード
真面目に定時出社し、責任感を持って仕事に取り組んでいる社員は、遅刻や欠勤を繰り返す社員を目の当たりにすることで、「なぜあの人は許されるのか」という不公平感を抱くようになります。この不満が組織全体に蔓延すると、従業員の会社に対する信頼は失われ、エンゲージメントは低下します。
そして、やがて「真面目に働くのが馬鹿らしい」という風潮が広まり、規律が緩んでいく「モラルハザード」が起きてしまうかもしれません。一人を放置した結果、会社全体の規律が崩壊し、勤怠不良者が増えるという負の連鎖に陥るリスクがあるのです。
(2)生産性の低下と業務の停滞
特定の社員の遅刻や欠勤は、チーム全体の業務計画を狂わせます。その社員が担当していた業務を、他のメンバーが急遽カバーしなければならず、本来の業務に手が回らなくなるからです。
特に、顧客対応や納期が厳格に定められているプロジェクトでは、突発的な勤怠不良が取引先からの信頼を損ない、会社の信用問題に発展する可能性もあります。全体の生産性が低下するだけでなく、特定の社員の業務が滞ることで、会社全体としての目標達成が困難になることも珍しくありません。
(3)コストの増加と無駄なリソース消費
遅刻や欠勤が続く社員の業務を他の社員が代行する場合、その分の残業代や人件費が増加します。また、新たな人材を採用・教育するために費やしたコストが、結果として戦力にならないことで無駄になってしまいます。
さらに、この問題を放置すると、最終的に解雇を検討せざるを得なくなる可能性が高まります。その際に、適切な手続きを踏んでいなかった場合、不当解雇として訴えられ、多額の賠償金を支払うリスクも生じます。訴訟対応にかかる弁護士費用や時間、精神的負担まで含めると、そのコストは膨大なものとなります。
(4)法的リスクの増大
最も注意すべきは、この問題について誤った判断をしてしまう危険、そのことによって会社が法的リスクを負う点です。
例えば、勤怠不良が原因でいきなり解雇を言い渡した場合(このこと自体が誤った判断ですが)、社員側から「指導・改善の機会を与えられていない」として、不当解雇であると訴えられる可能性が非常に高いです。日本の裁判所は、解雇の有効性を判断する際に、会社がどれだけ改善を促すための努力をしたかを厳しく評価します。
また、会社が遅刻や欠勤を繰り返す社員を放置した結果、その社員が心身の不調を訴えて休職に至った場合など、状況によっては会社が安全配慮義務違反を問われるリスクもゼロではありません。問題社員への対応は、感情的に行うのではなく、リスクを回避するための適切なプロセスだと捉えることが重要です。
2. 遅刻や欠勤を繰り返す問題社員への対応方法
問題社員への対応は、一足飛びに最終的な処分を考えるのではなく、段階的なステップを踏むことが重要です。これは、社員に改善の機会を与え、それでも改善が見られない場合に初めて、次のステップに進むというプロセスです。
(1)ステップ1 初期対応と事実確認
まずは、感情的にならず、冷静に事実を把握することから始めましょう。
① 事実の記録
勤怠管理システムやタイムカード、上司からの報告などを基に、いつ、何回、何時間遅刻・欠勤したのかを正確に記録します。この記録は、後の面談や書面での警告、最終的な懲戒処分を検討する際の客観的な証拠となります。曖昧な記憶ではなく、具体的な事実に基づいて対応を進めることが極めて重要です。
②初期段階のヒアリングと注意喚起
勤怠不良が始まったら、まずは直属の上司が本人の体調や状況を軽くヒアリングします。「最近、遅刻が続いているようだけど、何かあった?」等と声をかけることで、病気や家庭の事情など、深刻な原因が潜んでいる可能性を探ります。この段階では、厳しく追及するのではなく、まずは状況を把握し、寄り添う姿勢を見せることが大切です。
③正式な個別面談の実施
口頭での注意で改善が見られない場合、人事担当者や責任者が同席して、正式な面談を実施
します。その際のポイントを挙げていきます。
ア 面談の目的を明確にする
最近の遅刻や欠勤の多さなどの勤怠について話し合うためと事前に伝え、業務時間内に会議室などプライバシーに配慮した場所で行います。
イ 事実を具体的に提示する
「◯月◯日と◯月◯日に、合計◯回遅刻がありました」のように、事前に記録した事実を本人に示します。この提示のために前述の記録が重要となるわけです。
ウ 本人の言い分を丁寧に聞く
遅刻や欠勤の理由を本人に話してもらい、記録します。
エ 就業規則の確認と会社の期待を伝える
会社の就業規則(勤務時間、勤怠管理のルール)を改めて説明し、遅刻や無断欠勤が「就業規則違反」であることを明確に伝えます。その上で、「会社としては、〇〇さんに真面目に勤務してほしいと期待している」というメッセージを伝えます。
オ 改善が見られない場合のリスクを説明する
今後も改善が見られない場合、人事評価に影響することや、就業規則に則った処分を検討せざるを得なくなることを伝えます。
カ 面談記録の作成
面談の日時、参加者、話した内容、本人の反応、今後の改善計画などを詳細に記録し、双方で確認・保管します。このような地味なプロセスの積み重ねが退職勧奨の際や最終的に解雇せざるを得なくなった際に効果を発揮することになりますので面倒くさいと思わずにやっていきましょう。
(2)ステップ2:段階的な指導と文書化
面談後も改善が見られない場合は、指導をさらに具体化し、記録に残します。
① 書面による指導・警告
口頭での注意や面談だけでは不十分な場合、書面(指導書や改善勧告書)を交付します。
② 具体的な内容
「いつ、何回の遅刻があったか」「就業規則のどの条項に違反しているか」「今後、いつまでにどのように改善を求めるか」を明確に記載します。
③ 最終的な措置への言及
「今後も改善が見られない場合は、就業規則に基づき懲戒処分を検討せざるを得ません」という文言も盛り込みます。
④署名・捺印
本人に指導書や改善勧告書の内容を理解させ、署名や捺印を求めます。本人が拒否しても、会社が書面を交付した事実は変わらないため問題ありませんが、拒否した事実も記録に残しておきましょう。
2. 人事評価への反映
勤怠は、社員の職務遂行能力や会社への貢献度を測る重要な指標です。公正な人事評価制度があれば、勤怠状況を評価項目の一つとして反映させ、本人の給与や賞与に影響を与えることも有効な手段となります。
(3)ステップ3:最終的な措置
度重なる指導にもかかわらず、改善がまったく見られない場合は、最終的な措置を検討します。
①懲戒処分の検討
懲戒処分は、社員の行為の悪質性や反復性、過去の指導経緯などを総合的に考慮して決定します。
けん責・戒告: 始末書を提出させ、将来を戒める最も軽い処分です。
減給: 賃金の一部を減額する処分です。労働基準法で上限が定められています。
出勤停止: 一定期間、労働義務を免除し、その間の賃金を支払わない処分です。
懲戒解雇: 最も重い処分です。解雇予告手当の支払い義務がなく、退職金も不支給とする場合があります。ただし、その要件は極めて厳格であり、会社側が懲戒解雇に値するほどの悪質性や改善の見込みがないことを証明する必要があります。
懲戒対象行為と懲戒処分のバランスが取れていない場合には懲戒処分が無効となりますので、無駄欠勤や遅刻などを理由に懲戒解雇をすることは出来ないと端的に考えた方が良いと思います。
②退職勧奨
懲戒処分による解雇は大きなリスクを伴うため、まずは退職勧奨を検討することが最優先で検討すべき方法です。退職勧奨は、あくまで「退職を促す」行為であり、本人の自由な意思に基づいて退職合意を形成するものです。
ア 強制はNG
「辞めなければ解雇する」といった強要は、退職の強要にあたり、違法となる可能性があります。後日退職の意思表示が無効となったり、労働者に対する慰謝料の支払義務が生じたりするので注意が必要です。
イ 円満な解決を目指す
労働者に対して本来は支給要件を満たさない退職金(本来は支払い義務がないものです)の支払いや会社都合退職での処理など、円満な解決を促すための条件を提示することも有効です。
3. 対応する際の注意点
問題社員への対応は、一歩間違えれば、ハラスメントや不当解雇として訴えられるリスクを常に伴います。以下の点に細心の注意を払いましょう。
(1)就業規則の整備と周知徹底
懲戒事由や懲戒処分の種類、勤怠に関する規定が、就業規則に明確に定められていることが大前提です。また、その就業規則が全従業員に周知されているかどうかも重要です。
(2)一貫性と公平性の確保
特定の社員だけを厳しく追及すると、パワハラや差別と訴えられるリスクがあります。全従業員に対して、同じ基準で、同じ手続きを踏んで対応することが不可欠です。
(3)証拠の記録と蓄積
指導面談の記録、指導書の控え、勤怠記録、業務上の支障に関する記録など、あらゆる証拠を時系列で整理・保管しておきましょう。これらの客観的な証拠は、万が一、裁判になった際に、会社の対応の正当性を証明する最も重要な武器となります。
(4)安易な「病気」判断は禁物
本人が体調不良を訴えた場合、安易に私傷病休職を勧めたり、反対に指導を諦めたりするのはリスクがあります。まずは医師の診断書提出を求め、産業医面談を促すなど、客観的な事実に基づき状況を把握することが重要です。
(5)プライバシーへの配慮
本人の体調や家庭の事情など、個人的な情報を他の従業員に漏らさないよう、最大限の配慮を払いましょう。
4. 問題社員対応に関して弁護士に相談するメリット
問題社員対応は、法的なリスクが複雑に絡み合う専門性の高い分野です。特に、懲戒処分や解雇を検討する際には、弁護士に相談することが極めて重要となります。
(1)法的リスクの正確な判断
弁護士は、懲戒処分や解雇が法的に有効か、不当解雇と判断されるリスクはないかなど、専門的な見地から正確なアドバイスを提供します。これにより、予期せぬ訴訟トラブルを回避し、リスクを最小限に抑えることができます。
(2)具体的な対応策の策定
個々のケースに合わせた具体的な指導方法、面談での話し方、書面の文言などについて、実践的な助言を得られます。弁護士が監修・作成した書面は、法的な有効性が高まります。
(3)第三者としての客観的な視点
感情的になりがちな問題社員対応において、第三者である弁護士の冷静かつ客観的な視点は不可欠です。会社側の立場に寄り添いつつも、法的な観点から最善の道筋を示してもらえます。
(4)紛争の代理交渉
不幸にして社員側とトラブルになった場合、弁護士が代理人として交渉にあたることができます。退職勧奨や和解交渉を円滑に進める上で、弁護士の存在は大きな力となります。
問題社員への対応は、会社にとって大きな負担となります。しかし、適切なプロセスを踏んで対応することで、組織の規律を守り、社員のモチベーションを維持し、そして何よりも会社を守ることにつながります。
もし、貴社でも同様の問題に直面しているのであれば、決して放置せず、早期に専門家である弁護士に相談し、適切な対応を検討されることを強くお勧めします。
6.当事務所のサポート内容
当事務所は既に裁判や労働審判に至っているケースにおける会社側の代理人としての対応、労働者側に代理人弁護士が付いている交渉における会社側の代理人としての対応をスポットで行うケースもありますが、基本的には会社と顧問契約を締結して顧問業務の範囲内で日常の問題社員対応(本件のような遅刻・欠勤が多い社員に対してどのような対応をすればよいのかという相談を顧問先から受けることも珍しくありません。)に関する相談対応や懲戒処分の適用についての助言などを行い、不幸にして係争に発展した場合も顧問弁護士として引き続き会社側の代理人弁護士として対応していくことにしております。
労使紛争に発展しているケースにおいても既に発生している労使紛争の解決にとどまらず労使紛争に至った原因を除去して今後の紛争を予防する必要がありますので、紛争状態にある会社と顧問契約を締結してその業務として労使紛争における会社側の代理人として対応をするケースが多いです。紛争の解決と今後の紛争予防に向けた取り組みを並行して行っていくイメージです。
労使紛争に既に巻き込まれており対応に苦慮されている会社経営者の皆様、問題社員対応に苦慮されており日常的に弁護士へ相談することで悩みを1人で抱え続ける精神的な負担を軽減したいとお考えの経営者、人事担当者の皆様、当事務所との顧問契約の締結をご検討されることをお勧めいたします。
文責 弁護士 浜田 諭
- 円満退職を叶える退職勧奨のポイント|企業法務に詳しい弁護士が解説
- 債権回収を弁護士に依頼するメリットと判断基準について解説
- 既に退職した社員から現場への直行直帰を伴う就労について現場への移動時間、現場からの戻り時間についても労働時間であり、この時間について賃金が支払われていないことを理由に未払い賃金を請求されたものの元社員の請求額を大幅に削った内容の判決から付加金を削った内容にて控訴審が判決を下し、これが確定して解決した事例
- 懲戒解雇とは?懲戒解雇が認められる場合、認められない場合について、弁護士が解説
- 【ご報告】代表弁護士柏田笙磨が国際ロータリー第2730地区の危機管理委員(弁護士)に選任されました
- 解雇の種類と注意すべきポイントを弁護士が解説
- 問題社員について解雇するのではなく交渉によって会社都合退職という形で合意退職による解決ができた事例
- 遅刻や欠勤を繰り返す問題社員を放置するリスクとは?企業が知っておくべき対応方法について弁護士が解説
- 業務の指示に従わない社員にどう対応する?問題社員対応について弁護士が解説
- 非違行為のある社員とは?企業の適切な対応方法について弁護士が解説