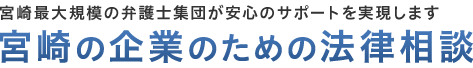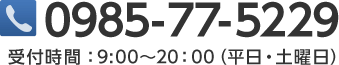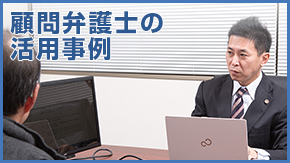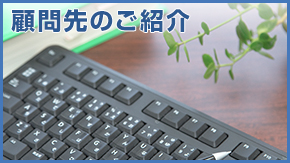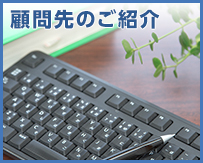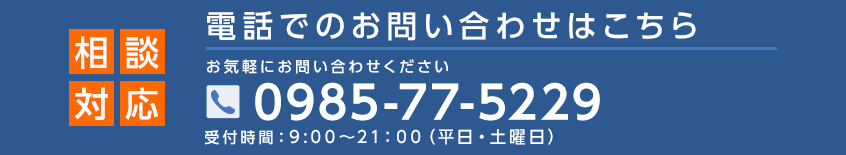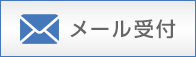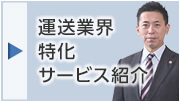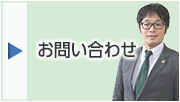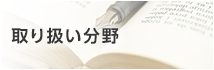ハラハラ(ハラスメントハラスメント)への対応について弁護士が解説
今回は最近話題になることが多くなったハラハラすなわちハラスメントハラスメントについてお話ししていこうと思います。
お話しする内容は以下のとおりです。
1 ハラハラ(ハラスメントハラスメント)とは
2 ハラハラの具体例
3 ハラハラが起こる背景と社会的構造
(1)ハラスメントが起こる背景と社会的構造
(2)通報制度の濫用
(3)SNS等による告発文化
4 ハラハラを防ぎつつ、必要なハラスメント対策を実現するためのポイント
(1)指導記録・面談記録を残す
(2)判断基準の明確化・管理職に対する研修
(3)第三者によるチェック機能の整備
5 ハラスメントに関して弁護士に相談するメリット
6 当事務所のサポート内容

それでは早速内容に入っていきましょう。
近年、職場におけるハラスメント対策は、企業にとって喫緊の課題となっています。
パワハラ防止法をはじめとする法整備が進み、企業はハラスメントのない健全な職場環境づくりに積極的に取り組む必要に迫られています。
しかし、その一方で、ハラスメント対策が過剰に進むことで、本来ハラスメントに該当しない言動までがハラスメントとして問題視される「ハラハラ(ハラスメントハラスメント)」と呼ばれる現象が顕在化しつつあります。
本稿では、このハラハラの実態、それが起こる背景にある社会的構造、そしてハラハラを防ぎつつ本当に真に必要なハラスメント対策を実現するためのポイントについてお話していこうと思います。
1 ハラハラ(ハラスメントハラスメント)とは
ハラハラ、すなわちハラスメントハラスメントとは、ハラスメントに該当しない、あるいはその可能性が低い言動に対して、ハラスメントであると一方的に主張したり、過剰に反応したりする行為を指します。これは、ハラスメントという言葉の射程が広がり、社会全体のハラスメントに対する感受性が高まる中で生じている現象と言えるでしょう。
具体的には、上司や先輩からの建設的な指導や注意、業務上必要な指示、同僚間の些細なコミュニケーションなどが、受け取る側の主観的な解釈によってハラスメントであると認識され、被害申告や告発につながるケースがこれに当たります。
また、ハラスメント被害申告を手段として、個人的な不満を解消したり、自己の優位性を確立しようとしたりする悪質なケースも存在しています。
ハラハラは、真摯なハラスメント対策の取り組みを阻害し、健全な職場環境を損なうだけでなく、本当にハラスメント被害を受けた方にとって不当な精神的負担や風評被害をもたらす可能性があります。また、ハラハラが横行することで、本当にハラスメントに苦しんでいる被害者の声が埋もれてしまう危険性も否定できません。
ハラハラと評価されたくないからハラスメント被害を申告しないという萎縮効果が生じては本末転倒です。
2 ハラハラの具体例
ハラハラの具体的な事例をいくつか見ていきましょう。これらの例は、本来ハラスメントに該当しない可能性のある言動が、受け手の過剰な反応や主観的な解釈によってハラスメントとして扱われてしまう具体例となります。
例1: 上司が部下の提出した報告書に対し、具体的な改善点を指摘し、再提出を求めたところ、部下が「自分の能力を否定されたと感じる。パワハラだ」と主張する。
例2: 先輩社員が新入社員に対し、業務の進め方についてアドバイスをした際、新入社員が「細かすぎる指導で息が詰まる。モラハラではないか」と不快感を示す。
例3: 同僚間の軽い冗談やからかいに対し、言われた側が「人格を傷つけられた。ハラスメントだ」と訴える。
例4: 業務上の役割分担や責任範囲について明確にするための指示が、「特定の個人に負担を強いるものだ」としてパワハラであると被害申告する。
例5: 過去の些細な言動を蒸し返し、「あの時の言動はハラスメントだった」と被害申告してくる。退職後に在職中のハラスメント被害があったとして慰謝料請求をしてくるパターンが多い。
例6: ハラスメント通報制度を利用して、日頃から不満に思っている上司や同僚を陥れようとする。
これらの例は、コミュニケーション不足、認識のずれ、過度な被害者意識、あるいは悪意のある意図など、様々な要因によってハラハラが生じうることを示唆しています。
3 ハラハラが起こる背景と社会的構造
ハラハラという現象が生じる背景には、以下のような複合的な要因が存在します。
(1)ハラスメントが起こる背景と社会的構造
近年、ハラスメントに対する社会的な意識は著しく高まっています。メディアによる報道や啓発活動、そして法整備の進展により、ハラスメントは決して許されない行為であるという認識が広まりました。これは、これまで泣き寝入りを余儀なくされてきた被害者にとって、声を上げやすい社会になったという点で大きな進歩と言えるでしょう。
しかし、その一方で、ハラスメントという言葉の定義や範囲が広がり、曖昧になっている側面も否定できません。「〇〇ハラスメント」という言葉が濫用され、本来はハラスメントに該当しないような言動までがハラスメントとして認識される傾向があります。また、職場における上下関係やコミュニケーション不足、個人の価値観や感受性の違いなども、ハラスメントの発生要因となるだけでなく、ハラハラを生み出す土壌となり得ます。
(2)通報制度の濫用
多くの企業でハラスメントに関する通報制度が整備されていますが、この制度が必ずしも健全に機能しているとは限りません。制度の趣旨とは異なり、事実に基づかない被害申告や、個人的な不満や報復感情を解消するための手段として通報制度が利用されるケースが見受けられます。
このような通報の濫用は、 ハラスメントの被害申告によって加害者とされた側の精神的な負担はもとより、通報を受けた窓口や担当部署においても事実確認に多大な時間と労力を費やすことになり、企業の業務効率を低下させる要因となります。
さらに、安易な通報が繰り返されることで、本当に支援を必要とするハラスメント被害者の声が埋もれてしまうという深刻な問題も引き起こしかねません。通報制度は、被害者を救済するための重要な仕組みであると同時に、その適切な運用が求められています。
(3)SNS等による告発文化
インターネットやSNSの普及は、情報発信のあり方を大きく変えました。匿名性の高さから、誰もが容易に情報を発信できるようになった一方で、真偽が不明な情報や一方的な主張も拡散されやすくなりました。ハラスメントに関する告発も例外ではなく、事実確認が不十分なままSNS上で拡散され、関係者の名誉や信用を著しく毀損する事例が後を絶ちません。
また、「告発すること=正義」という短絡的な思考や、 被害者を擁護しているという正義感や自分は良いことを行っているという自己満足感を持つタイプのSNS利用者の未熟な感情をを利用して特定の個人や組織を攻撃しようとする風潮も、ハラハラを助長する要因の一つと言えるでしょう。
このような告発文化は、社会全体のハラスメントに対する意識を高める一方で、安易な告発や誹謗中傷を生み出し、何がハラスメントであり、どのような対処が必要なのか等についての健全な議論を妨げる可能性も孕んでいます。
4 ハラハラを防ぎつつ、必要なハラスメント対策を実現するためのポイント
ハラハラという負の側面を抑制しつつ、真にハラスメントのない健全な職場環境を実現するためには、企業は以下の点に留意し、具体的な対策を講じる必要があります。
(1)指導記録・面談記録を残す
日々の業務における指導や注意、部下との定期的な面談内容を詳細かつ客観的な記録として残すことは、ハラスメント被害申告が発生した際の重要な証拠となります。記録には、日時、場所、参加者、具体的な指導・注意の内容、その意図や目的、部下の反応や意見などを具体的に記載することが重要です。
これらの記録は、 被害申告の内容が事実に基づいているかどうかを判断する上で役立つだけでなく、指導者自身が自身の言動を振り返り、改善に繋げるための貴重な資料となります。
また、記録を残すという行為自体が、ハラスメントに対する意識を高め、予防効果にも繋がる可能性があります。
(2)判断基準の明確化・管理職に対する研修
何がハラスメントに該当するのか、その明確な判断基準を社内で共有し、従業員全体に周知徹底することが不可欠です。就業規則やハラスメント防止規程に具体的な定義や事例を盛り込み、定期的な研修や説明会を通じて従業員の理解を深める必要があります。
特に、部下を持つ管理職に対しては、ハラスメントに関する知識だけでなく、適切な指導方法、コミュニケーションスキル、部下の多様な価値観への理解などを習得するための研修を継続的に実施することが重要です。管理職の言動は、部下にとってハラスメントと感じられるかどうかの重要な分かれ目となるため、その意識改革とスキルアップは急務と言えるでしょう。
(3)第三者によるチェック機能の整備
ハラスメントに関する被害申告があった場合、当事者間の主張だけでなく、客観的な視点からの事実調査と判断を行うための第三者によるチェック機能を整備することが重要です。社内の人事部門だけでなく、外部の専門家(弁護士、社会保険労務士、カウンセラーなど)に相談できる体制を構築することも有効です。
また、 ハラスメント被害申告の受付窓口を複数設置したり、匿名での相談を可能にしたりするなど、被害者が安心して相談できる環境を整備することも大切です。
ハラスメントの被害申告を受けた処理のプロセスにおいては、公平性、透明性、迅速性を確保し、 被害申告者と被申告者(すなわち加害者とされている)者の双方に配慮した対応が求められます。
5 ハラスメントに関して弁護士に相談するメリット
ハラスメントに関する問題が発生した場合、早期に弁護士に相談することには多くのメリットがあります。弁護士は、法律の専門家として、事実関係について法的評価を踏まえて整理し、適切なアドバイスを提供することができます。
まず、ハラスメント被害申告の内容が法的にどのような意味を持つのか、企業がどのような責任を負う可能性があるのかについて、正確な法的見解を得ることができます。これにより、会社は安易にハラスメント被害を認定して対処してしまう場合の法的リスクを回避し、適切な対応方針を立てることが可能になります。
次に、弁護士は、会社側に立ってハラスメント被害申告者や被申告者(加害者とされている者)との交渉を代理人として行うことができます。感情的な対立がある場合でも、第三者である弁護士が介入することで、冷静かつ客観的な話し合いを進めることが期待できます。
また、必要に応じて、事実調査のサポートや、証拠収集のアドバイスを受けることもできます。
さらに、ハラスメント問題が訴訟に発展した場合、弁護士は会社の代理人として訴訟手続きにおける主張立証、そのための書面提出等を全面的にサポートし、企業の権利と利益を守ります。
訴訟において会社が被る被害(例えばハラスメントがあったと認定された場合の損害賠償額)を最小限に抑えるための戦略を立て、適切な主張や証拠提出を行うことで、 会社の負担を軽減することができます。
加えて、弁護士は、問題解決後の再発防止策の策定についても支援することができます。過去の事例を踏まえ、法的な観点から実効性のある対策を講じることで、将来的なハラスメント発生のリスクを低減することが期待できます。
結論として、ハラスメント問題は、企業経営に深刻な影響を与える可能性のある重要な課題です。
ハラハラという新たな問題にも目を向けつつ、真に必要なハラスメント対策を講じるためには、法的専門家である弁護士の知識と経験を積極的に活用することが、会社aにとって賢明な選択と言えるでしょう。
弁護士への早期の相談とその助言を踏まえた適切な対応が、健全な職場環境の維持と会社の持続的な発展に不可欠です。
6 当事務所のサポート内容
当事務所は多くの会社の顧問業務を日常的に行っており、顧問業務の中でハラスメント被害の申告が社内で生じた場合の対処の助言、紛争化した場合の会社の代理人としての交渉対応、訴訟対応、ハラスメント防止のための対策の助言などを行っております。
ハラスメントへの対応、紛争化した場合の対応、再発防止への取組みなどを総合的に対処するためには被害が生じた場合のスポットでの対応よりも常日頃からの会社の業務や社内での人間関係を理解した上での対応が可能な顧問業務を弁護士に依頼されることをお勧めします。
当事務所との顧問契約を検討されたい会社経営者の皆様,人事担当者の皆様は遠慮なくお問い合わせください。
- 退職代行を使われたらどうする?対応のポイントについて弁護士が解説
- 円満退職を叶える退職勧奨のポイント|企業法務に詳しい弁護士が解説
- 債権回収を弁護士に依頼するメリットと判断基準について解説
- 既に退職した社員から現場への直行直帰を伴う就労について現場への移動時間、現場からの戻り時間についても労働時間であり、この時間について賃金が支払われていないことを理由に未払い賃金を請求されたものの元社員の請求額を大幅に削った内容の判決から付加金を削った内容にて控訴審が判決を下し、これが確定して解決した事例
- 懲戒解雇とは?懲戒解雇が認められる場合、認められない場合について、弁護士が解説
- 【ご報告】代表弁護士柏田笙磨が国際ロータリー第2730地区の危機管理委員(弁護士)に選任されました
- 解雇の種類と注意すべきポイントを弁護士が解説
- 問題社員について解雇するのではなく交渉によって会社都合退職という形で合意退職による解決ができた事例
- 遅刻や欠勤を繰り返す問題社員を放置するリスクとは?企業が知っておくべき対応方法について弁護士が解説
- 業務の指示に従わない社員にどう対応する?問題社員対応について弁護士が解説