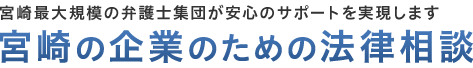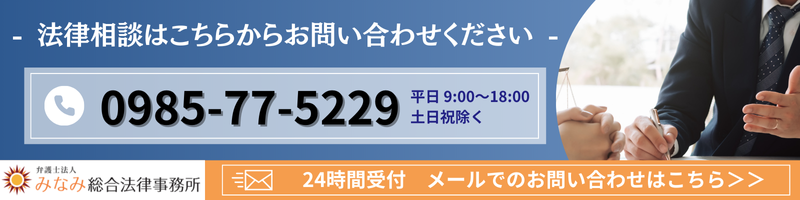弁護士が解説!債権回収の時効 ~権利が消滅する前に知っておくべきこと~
今回は、見落とされがちである債権回収の時効に関する危険性についてお話していこうと思います。
今回お話しする内容の項目は下記のとおりです。
それでは、早速内容に入っていきましょう。
1.債権回収とは
(1)債権回収の重要性
人が人に一定の行為を求める権利を「債権」といいます。中小企業の経営者の方がイメージしやすい債権は、売買した商品やサービスに対してお金の支払いを求める債権だと思います。これは売買代金債権ですね。
この債権という権利を持っていても、行使しなければ債務者(この例だと商品やサービスを購入した代金を支払う義務を負う会社や人)が義務を果たさないこともありますし、権利を行使しないまま一定の期間が経過すると消滅時効にかかって行使できなくなってしまうこともあります。この点は後述します。
債権の管理、特に回収をきちんと行わない、と売掛(代金後払い)で提供した商品やサービスの対価が支払ってもらえなくなる可能性がありますし、そのことが会社の経営に与える悪影響は深刻です。この悪影響について、具体的に考えていきましょう。
(2)債権の未回収が企業に与えるリスク
会社は営利法人であり、事業を通じて利益を得ることを目的としています。
例えば製造業は材料を仕入れて商品となる物を製造し、これを売却する際に、それまでにかかったコストや販売管理費を考慮した利益を上乗せした代金で売却します。売却する先は一般消費者のこともありますし、卸売業者や小売店に売却することもあるでしょう。会社の一連の取引は商品を売却した時点で完結するわけではなく、売買代金が回収できたタイミングで完結すると考えても良いと思います。
そして、売買の場面で言えば、売主が買主から売買代金を支払ってもらう権利が「債権」です。債権が未回収ということは、その取引によって得ようとしていた利益のみならず、その商品を提供するまでにかかったコストが代金によって補填されないということを意味します。
会社は、かかった費用を補填できないまま営業活動を続けると、当然ですが、会社の財務内容は悪化して赤字経営に陥ることもありますし、金融機関から借り入れた事業資金についての返済ができなくなる、次の商品を製造するための材料を仕入れることができなくなる、社員への給与が支払えなくなるという深刻な事態にもつながりかねません。
そして債権の未回収が積み重なること、大口の債権の未回収が生じたことが、最終的には会社の倒産につながるケースも珍しくないのです。
2.債権回収における時効の影響
(1)時効とは
時効というのは、ある事実状態(たとえば、当事者間に債権債務が存在しないかの状態)が、所定の期間継続した場合に、その事実状態に対応する権利関係を認める制度です。
例えば、人に対してお金を請求する権利(債権)を持っている人(債権者)がいて、その人が相手方(債務者)に請求しないまま時間が経つと、そもそもこの2人の間にはお金を支払ってもらう権利や、支払わなくてはいけない義務がないように見えますよね。この状態を尊重して、権利を消滅させてしまうというのが消滅時効というものです。
この消滅時効については、債権が自然に消滅するというものではなく,債権者が債務者に対して権利を行使した際(お金を支払ってくれと請求した際)、その権利は消滅時効にかかっているので支払えませんと主張する(これを「時効の援用」といいます。)ことによって権利が消滅することになります。
債権回収を含めた債権管理において最も気を付ける必要があるのは、債権を消滅時効にかけないということです。消滅時効にかかっている債権について請求されて、支払うような会社はほぼありませんから、権利を消滅時効にかけたタイミングで回収不能になったと評価して良いでしょう。
(2)時効成立までの期間
令和2年4月1日に改正民法が施行されるまでの間、債権はその種類によって消滅時効期間が細分化されていました。このことによって債権管理は非常に煩雑な面がありました。
しかし、令和2年4月1日以降に行われた法律行為(例えば契約)によって発生した債権については改正民法が施行されますので、基本的に以下の内容で考えればよいことになります。
権利を行使することができる時(これを「客観的起算点」と呼びます)から10年(民法166条1項2号)、または権利行使することができ、かつ、債権者が権利を行使することをできることを知った時(これを「主観的起算点」といいます。)から5年を経過するときに消滅時効は完成します。
「権利を行使することができる」とは、権利の行使につき法律上の障害がなく、さらに権利の性質上、行使を現実に期待することができることをいいます(最判平21・1・22等)。
法律上の障害がある場合の典型例は、債権に停止条件や期限が付されている場合です。
わかりやすいのは期限が付されている場合で、商品を売却する売買契約を締結し、その契約において、売買代金の支払期限を契約日の1か月後にした場合、この支払日が「権利を行使することができる」時点になります。契約をした日には売買代金を請求できず、支払日が到達してからようやく売買代金を請求できるようなる、「権利を行使することができる」ようになると考えるとわかりやすいと思います。
そして「権利を行使することができると知った時」とは、その債権者による権利の行使を現実的に期待することができることとなった時点をいいます。債権者がどのような事実を知ったときがこの時点と評価されるかは、事案ごとの判断になるのですが、債権管理を考える会社経営者、担当者の皆様はシンプルに以下のように考えていただくのが良いと思います。
契約から発生して支払期限がきまっている債権は、「権利を行使することができる」時点(客観的な起算点)において、その権利を行使できることを知っているので、5年で消滅時効にかかることになるということです。
ここをしっかり押さえた上で、この例外を考えていくようにしてください。具体的に考えてみましょう。
例えば、商品を代金後払い(契約の1か月後が支払期限とします)で売った場合、客観的な起算点は契約の1か月後です。いつから権利行使をすることができるか(売買代金を支払ってもらえるか)は契約の時点でわかっていますから、支払期限の時点で権利を行使することができるのを知っています。このことから、売買代金の支払期限から5年で消滅時効が完成することになるのです。
(3)時効の完成猶予と更新
債権を消滅時効にかけないようにするには時効の完成前に回収に着手して、時効が完成しないようにする必要があります。消滅時効の完成を一時的に止めて、消滅時効期間をリセットする必要があるのです。一時的に止めることを時効の完成猶予、消滅時効期間をリセットすることを、時効の更新と呼びます。旧民法では、暫定的な時効中断、時効の中断と呼ばれていたものになります。
実務上もっともわかりやすいものを例に挙げて説明します。
売買代金を買主が支払ってくれない場合、債権回収のために何をするかというと、電話をして支払いをお願いしますと伝える、請求書を送るというのが最も一般的ですよね。このような請求する行為を「催告」といいます。
この催告によって、催告の到達時から6か月経過するまでは、時効が完成しません(民法150条1項)。これを催告による時効の完成猶予といいます。
口頭での請求も「催告」なのですが、口頭でのやり取りは言った言わないの争いになることが多いので、文書で請求書を送ることが多いですし、相手方に信用が置けないケースだと、文書を受け取っていないという反論を封じるために、請求書を内容証明郵便で送ることもあります。債権者としては、「催告」をしたこと、それが債務者に到達したことを後から立証できるようにするためです。
話が少し本筋から外れましたので元に戻します。
実務上よく見るのが、請求書を送って支払ってもらえないから再度請求書を送るということを繰り返しているケースです。この場合、時効の完成猶予は最初の請求書の到達時から6か月までしか生じず、2本目以降の請求書には時効の完成猶予の効果は生じません。最初の請求書が債務者に到達してから6か月経過するまでに回収できていない場合には、消滅時効の期間をリセットするために、(時効を更新するために)民事訴訟を提起するなどのアクション(「裁判上の請求」等)を起こさないといけないのです。
例えば、請求書を何度か送っても支払ってもらえないまま支払期限から4年6か月が経過した時点で、時効を完成させてはいけないと考えて、再度請求書を送っても、時効の完成は猶予されません。進んでしまっている4年6か月をリセットして0に戻すには、残りの6か月の間に民事訴訟を提起するか、債務者から支払いますという文書をとるか(債務の承認をしてもらうか)のいずれかの対応をしないと、消滅時効が完成してしまうのです。
時効の更新が生じた場合には、既に進んでいる時効期間がリセットされて0に戻り、そこから新しい時効が進行することになります。なお、消滅時効期間を更新するために民事訴訟を提起するというよりは、債権回収を図るために民事訴訟を提起する、その結果としてその時点で回収できなくても時効は更新される、という発想が自然だと思います。
なお民事訴訟で債務者に対して金銭の支払いを命じる判決が下されて確定した場合には、その時効期間は10年とされています(民法169条1項)。
3.債権回収の方法
この点については以前掲載したコラムをご参照ください。
4.自分で債権回収をするデメリット
(1)専門知識の欠如
債権回収には、民法などの実体法の知識と民事訴訟法、民事保全法、民事執行法といった手続法の知識が必要であり、どのタイミングで債務者にどのようなアクションを起こして回収を図るかについては、机上の知識に加えて実際に回収業務を行った経験が必要になります。
このような経験がない一般の方が、専門知識もないのに回収業務を行うというのは、非常にハードルが高いといえるでしょう。
(2)自己回収の労力とコスト
専門知識がないことを行うには多大な労力と時間がかかります。これは債権回収においても同様であり、自分で(自社で)やってみたものの、担当者が膨大な時間と労力をかけて日常の業務に穴をあけてまで行ったのに、それほど回収できなかったという結論になると、目も当てられません。債権回収は既に終わった取引から発生したものを回収するという、それ自体が新しい価値を生み出さないものになり、そこに会社の貴重な人材の労力と時間を費やすくらいであれば弁護士に依頼して、自社は本来の業務に注力するというのが合理的だと考えます。
(3)時効の見落とし
前述のように、請求書を何度も送り続けて法的なアクションを起こさずに、債権を消滅時効にかけてしまう会社も散見されますし、専門知識の欠如は、時効の見落としによって、本来回収できたはずの債権を消滅時効にかけてしまうという、債権管理における最悪の結論につながる危険もあります。
5.債権回収を弁護士に依頼するメリットと必要性
債権回収にあたっては、裁判所を使った民事訴訟等の手続、その手続に向けた交渉を行うことになりますので、法律の専門家である弁護士のサポートを得るのが最も合理的です。また、どの弁護士に依頼しても債権回収業務を行うことはできますが、緊急性がある場合の保全処分や、民事訴訟によって得た債務名義(強制執行を行うことができる根拠となる文書のことで、裁判所が下した判決(確定したもの)、裁判所で交わされた和解の調書等)を使って強制執行をする場合の、ノウハウや経験を持っている弁護士に依頼するのが最も適切だと思います。
民事訴訟を提起して争っている間に資産隠しをされてしまう場合に、保全処分をすることができるかどうかが重要となるケースもありますし、裁判所が下して確定した判決があっても支払わない債務者に対しては、強制執行を使った回収が必須となるからです。
不払いの場合には民事訴訟を提起することを想定して債権の回収を行う交渉の段階、交渉が決裂した場合の民事訴訟、民事訴訟に先行して債務者の財産を保全する仮処分、仮差押といった保全処分、債務名義をとった後にも支払わない債務者への強制執行、のいずれの場面でも弁護士を代理人に立てるのが、正確な法的知識に裏付けられた最も手堅く、効率的な債権回収をすることにつながります。
6.まとめ
当事務所は民事訴訟を提起する形(訴訟代理人として対応する形)での債権回収はもちろん、民事訴訟提起を視野に入れた交渉業務、交渉と民事訴訟の間に債務者の財産を保全する民事保全(仮差押え、仮処分等)、債務名義をとった後の強制執行のいずれの段階においても、経験と能力を持った弁護士が在籍しております。
自社での債権回収が上手くいかず、弁護士によるサポートを得て回収業務を行う必要性を考えておられる会社経営者の方、債権管理を担当されている役員、社員の方からの問い合わせをお待ちしております。
文責 弁護士 浜田 諭