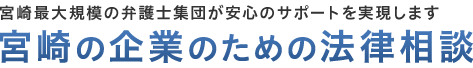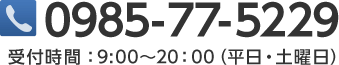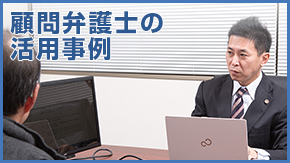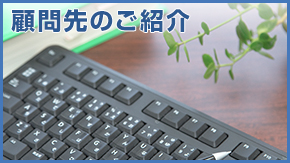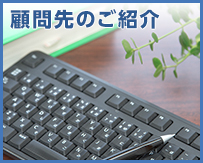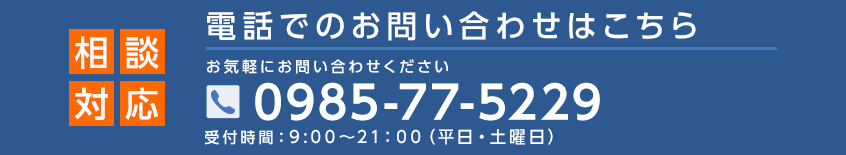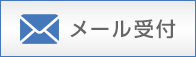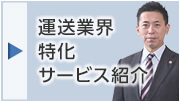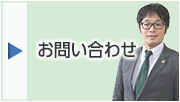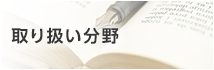就業規則の作成における注意点とは?~宮崎の弁護士が、中小企業にとって重要な就業規則を解説~
この項目では就業規則について書いていこうと思います。お伝えする項目は以下の内容となっております。
1 就業規則の重要性・役割
・コンプライアンスの視点と労働条件の設定という視点
2.作成・変更する際のポイント
(1)そもそも作成義務があるのか
(2)記載事項について
(3)労働者代表からの意見聴取
(4)届出手続
(5)周知手続き
3.自社で作成するデメリット
法的リスク
知識不足
時間と労力の浪費
4.当事務所のサポート内容
5.当事務所に依頼するメリット
それでは早速内容に入っていきましょう!
1 就業規則の重要性・役割
就業規則とは,労働者の労働条件などについて使用者が作成する書面ですが,実務上,以下の2つの意味で重要です。
1つ目は労働基準法を遵守するという意味です。
使用者は労働基準法で定める手続きと内容を満たした就業規則を作成・周知しなければなりません(労基法89条,90条,106条)。これに違反すると刑罰が科されることになりますので労基法を守るという企業のコンプライアンス(法令遵守)としての意味を持っています。就業規則作成のルール違反は労働基準監督署の取り締まりの対象となりますし(労基法97条以下,120条1号),コンプライアンスという点からも重要と言えます。
2つめは,就業規則が労働条件の設定をする効果を持っているからです。
就業規則で定める合理的な労働条件が使用者と労働者の労働契約の内容となりますので,企業内の使用者と労働者との間の労働条件に関する権利義務関係を定めるという意味があります(労働契約法7条)。
2 作成・変更する際のポイント
(1)そもそも作成義務があるのか
就業規則の作成が義務づけられているのは,常時10人以上の労働者を使用する事業場であり,使用者は事業場ごとに就業規則を作成しなければなりません(労基法89条)。この作成義務がある事業場についてはコンプライアンスの視点からも作成が必要ということになりますし,作成義務がない事業場については労働条件を設定するという視点から作成しておいた方が良いということになります。
(2)記載事項について
労働基準法は就業規則に記載すべき事項を定めており(89条1号~10号),これらの記載をしなければ就業規則の作成義務を果たしたことにはなりませんのでこれらの事項を就業規則の「必要的記載事項」といいます。
この中には,いかなる場合にも必ず記載されなければならない「絶対的必要記載事項」(同1号~3号)と「定めをする」(制度として行う)場合において記載されなければならない「相対的必要記載事項」があります。
絶対的必要記載事項は
① 始業・終業時刻,休憩,休日,休暇,交替制の場合の就業時転換に関する事項(1号)
② 賃金の決定,計算および支払い方法,賃金の締切および支払いの時期ならびに昇給に関する事項(2号)
③ 退職に関する事項(解雇事由を含む。3号)
となります。
相対的必要記載事項には
④ 臨時の賃金・最低賃金等に関する事項(4号)
⑤ 表彰・制裁に関する事項(9号。懲戒処分規定などが代表的)
等があります。
なお,労基法上義務づけられていない事項については就業規則に記載するかどうかは使用者に委ねられています。これを任意的記載事項といいます。
ちなみに「用語の定義」「規則の適用範囲」「採用手続」等については,就業規則で定めておいた方がよい事項です。
制服・服装,作業マニュアルなどは就業規則の形で定める必要はなく内規の形でも十分かと思います。
(3)労働者代表からの意見聴取
使用者は,就業規則の内容を作成した後,当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合から,もし過半数組合がない場合には労働者の過半数を代表する者から意見を聴かなければなりません(労基法90条1項)。
なお,ここに意見聴取というのは,積極的な協議や同意を要求するものではありません。過半数組合や代表者の意見が就業規則に反対であっても,その旨の意見を記載した書面を就業規則届出の際に添付すれば足ります。ただ,反対意見が出た場合にはその理由を検討して,就業規則の内容を再検討して反映させるか,労働者側に使用者の考え方を説明して理解を得る努力をするのが望ましいでしょう。
 (4)届出手続
(4)届出手続
就業規則を作成した場合には行政官庁に届けなくてはならない(労基法89条)とされていますが,この「行政官庁」は事業場を管轄する労働基準監督署のことです。就業規則を作成したら事業場を管轄する(通常は最寄りの)労働基準監督署に届け出ることになります。
(5)周知手続き
使用者は就業規則を常時,各作業場の見やすい場所に掲示し,または備え付け,あるいは就業規則自体を交付することのいずれかの方法によって行わなければなりません(労基法106条1項)。
この点,現在では就業規則を事業場の共有のフォルダに入れて社員全員が閲覧できる状態にするという形での周知(労基法規則52条の2を踏まえた対応です)をする会社が増えている印象があります。
3 自社で作成するデメリット
(1) 法的リスク
就業規則に記載すべき事項を記載しないこと,記載すべきではないことを記載することの両方に法的リスクがあります。労働基準法よりも労働者に有利に内容を就業規則に記載すると就業規則が優先されることになりますし,問題のある内容の記載を就業規則にしてしまうとその条項を根拠にした対応が裁判等で全て否定される結果にもつながりかねません。就業規則に記載する意味,記載しない意味,記載する場合のメリットとデメリット等,色々な配慮のもとに規則内容は確定されるのが良いと思いますが,これは「とりあえず入れておけばいい。」「こういう条項があったらいいな。」みたいな考えで作成された,いいかげんな就業規則には法的リスクがあるからだとご理解ください。
(2) 知識不足
就業規則を作成,変更するには労働基準法や関連法令の理解が必要不可欠であり,この点が不十分であると(知識不足であると)使えない就業規則,まずい就業規則が作成されることになります。その結果,法的リスクがあることは既に述べたとおりです。
(3)時間と労力の浪費
就業規則の作成,変更には一定の知識が必要であり,これを一朝一夕で身に付けることはできません。そして知識があるだけではだめで,実際にその就業規則の条項が使えるものになるのかを判断する経験が必要となります。
これらの知識や経験がない担当者が就業規則の作成,変更を行うと膨大な時間や労力がかかることになり,時間と労力の浪費が見過ごせないレベルに至ることもあります。
4 当事務所のサポート内容
主に顧問先様の依頼に基づいて就業規則の作成や変更を行っております。
作成を一から行うことは少ないのですが,「このように変更したいのだけど労働条件の不利益変更にあたらないか」,「不利益変更にあたるとしても合理性があると判断されるのか」といった相談を受けることは多いです。
実は就業規則の作成,変更よりも重要なのは既存の就業規則をどのように運用するのかだったりします。
例えば,問題社員に対して懲戒処分を下そうと考えると就業規則の懲戒に関する規定の適用,服務規律のどの条項に違反するのかの検討が必要となり,そのタイミングで就業規則を確認したところ,どの条項を適用すればよいのかわからないという会社経営者,総務担当者は多くおられます。
就業規則の作成のタイミングで社労士の先生などが関与されておられ,就業規則自体には問題がないケースが多く,悩みどころは就業規則をどのように適用してどのように運用するのかであるケースがほとんどだと思います。
労使の問題のうち就業規則の適用が問題となる場面で就業規則の変更自体が必要なケースは多くなく,どう適用するのかが問題となるケースがほとんどでここが弁護士に相談することで有益な助言が得られる場面です。
当事務所では就業規則の適用はもちろん,労使の問題についての顧問先からの相談に日常的に対応しております。
就業規則の作成,変更,その適用については基本的に顧問契約をいただいている法人,個人事業主向けに相談対応,作成,変更のご提案を差し上げているところです。当事務所の顧問契約の内容はこちらをご覧ください。
→https://miyazaki-kigyouhoumu.com/%e9%a1%a7%e5%95%8f%e5%bc%81%e8%ad%b7%e5%a3%ab
5 当事務所に依頼するメリット
当事務所には労使紛争において使用者側の相談に日常的に対応している弁護士が在籍しており,交渉,労働審判,民事訴訟のいずれの段階においても使用者側の代理人弁護士としてお役に立てることが多いと考えております。
ご相談,ご依頼いただければ,抱えておられるお悩みについて迅速かつ正確なアドバイス,紛争化した案件への着手,解決までのスピード等を実感していただけると思います。
当事務所では顧問契約をはじめ,労使紛争にお悩みの経営者の皆様向けに様々なサポートを準備しておりますので,興味をお持ちの会社経営者の皆様,遠慮なくご相談ください。

執筆者 弁護士 濵田 諭
▶契約書・各書面のリーガルチェックに関する記事はこちら
- 円満退職を叶える退職勧奨のポイント|企業法務に詳しい弁護士が解説
- 債権回収を弁護士に依頼するメリットと判断基準について解説
- 懲戒解雇とは?懲戒解雇が認められる場合、認められない場合について、弁護士が解説
- 解雇の種類と注意すべきポイントを弁護士が解説
- 遅刻や欠勤を繰り返す問題社員を放置するリスクとは?企業が知っておくべき対応方法について弁護士が解説
- 業務の指示に従わない社員にどう対応する?問題社員対応について弁護士が解説
- 非違行為のある社員とは?企業の適切な対応方法について弁護士が解説
- ハラハラ(ハラスメントハラスメント)への対応について弁護士が解説
- 建設業における契約書のポイントについて弁護士が解説
- 建設業における請負代金等の回収について