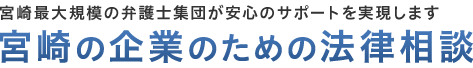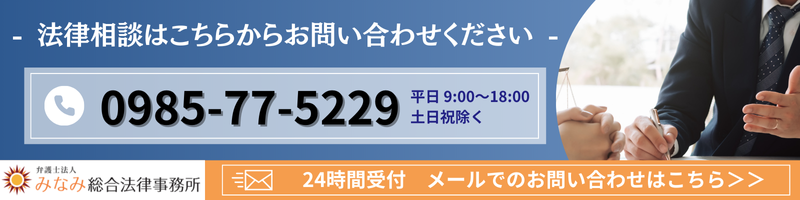【中小企業向け】人事担当者、会社経営者必見!違法にならない退職勧奨とは
今回は退職勧奨、特に違法とならない退職勧奨についてお話していこうと思います。
今回お話しする内容の項目は下記のとおりです。
第1 退職勧奨とは
第2 退職勧奨と解雇の違い
1 解雇は無効となるケースが多い!
2 解雇が無効となった場合の会社の不利益
(1)バックペイが生じる法的根拠
(2)バックペイのリスクとそれを超えるリスク
第3 退職勧奨が違法になるケースとその結果、会社にもたらされる不利益
第4 退職勧奨を行う方法・手順
1 置かれている現状や会社からの評価を社員に自覚させること
2 金銭解決の準備
3 会社都合退職での処理の検討
第5 当事務所のサポート内容
それでは早速内容に入っていきましょう。
第1 退職勧奨とは
退職勧奨とは、その名のとおり雇用者である会社側から労働者である社員に対して会社を退職するよう勧めることです。
あくまでも社員が退職するという自発的な意思表示を求める行為であり、それ自体は問題がありません。
ただ、後述しますようにやり方を誤ると退職勧奨が違法になるケースがあり、これは社員が行った退職の意思表示(通常は「退職届」や「退職願」といった文書が会社に提出される形で行われます)が取り消されて、退職自体がなかったことになるという効果が生じたり、退職勧奨自体が不法行為にあたるとして損害賠償責任を認められたりするケースもありますので注意が必要です。
しかし問題のない退職勧奨によって社員が退職してもらえれば時間、費用、労力のいずれの面においても会社側にはメリットしかありません。それにも関わらず問題社員の問題行動について、再三、目をつぶって我慢し続けてきた後で(問題行為に対する懲戒処分などもしていないケースがほとんどですが)堪忍袋の緒が切れて解雇してしまうという最も不合理な選択をする会社経営者は後を絶ちません。
そして、解雇した社員から不当解雇であると主張されて労働審判を申し立てられたり、社員の地位確認を求める民事訴訟を提起されたりして、社員の職場復帰を認めなくてはいけなくなるケース(割合的には多くありませんが)、多額の金銭を支払うのと引き換えに合意退職を内容とする和解を成立させなくてはいけなくなるケース(圧倒的に多いのは、このパターン)になるということですね。この手の紛争で会社側の代理人として紛争処理に関わるケースは、撤退戦を強いられる展開が最初から見えているケースがほとんどなので正直、気が重かったりします(私見)。そんなことを言い始めると労使の法的紛争が顕在化した後で使用者側の代理人をするケース全般に言えることだろうというツッコミが入りそうですが・・・。
冗談はさておき、退職勧奨について正確な知識を持っている会社経営者、人事担当者がかなり少ないというのが、日常的に労務管理についての相談を会社経営者側から受けている弁護士としての実感で、これが我慢の限界を超えたら即解雇という最悪の選択をする会社経営者が未だに見受けられる理由かなと思います。
前置きが長くなりましたが、基本的な知識から確認していきましょう。
第2 退職勧奨と解雇の違い
1 解雇は無効となるケースが多い!
退職勧奨は前述のとおり使用者である会社側から労働者である社員に対して会社を退職するよう勧めることですが、解雇は使用者である会社側からの申し出による一方的な労働契約の終了を指します。
解雇は、使用者がいつでも自由に行えるというものではなく、解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合には解雇することができないとされています(労働契約法第16条)。これは解雇権濫用法理と呼ばれるものです。
この「客観的に合理的な理由」は、4つに大別されるとされています。第1に、労働者の労務提供の不能や労働能力または適格性の欠如・喪失です。傷病 やその治癒後の障害のための労働能力の喪失、勤務成績の著しい不良、重要な経歴の詐称などによる信頼関係の喪失もここに入ります。
第2に、労働者の職場規律(企業秩序)の違反の行為です。懲戒処分がされるかわりに普通解雇がされるという場合です。
第3は経営上の必要性に基づく理由で、経営合理化による職種の消滅と他職種への配転不能、経営不振による人員整理(整理解雇)、会社解散などの場合です。
第4は、ユニオン・ショップ協定に基づく組合の解雇要求になります。そもそも、これら4つのいずれかに属するような「客観的に合理的な理由」が認められなければ、その解雇は解雇権を濫用したものとして無効となります。
そのような「客観的に合理的な理由」が認められる場合であっても、その解雇が「社会通念上相当として是認することができない場合」には、解雇権を濫用したものとして無効となります。
この相当性の要件については、裁判所は、一般的に、解雇の事由が重大な程度に達していて、他に解雇を回避する手段がなく、かつ労働者の側に宥恕すべき(寛大な心で許すべき)事情がほとんどない場合に解雇相当性を認めています。
ここまでを読んでいただければわかるように使用者による解雇が有効になるハードルは高く、裏を返すと解雇をしても無効になるケースがかなり多いということになります。
2 解雇が無効になった場合の会社の不利益
(1)バックペイが生じる法的根拠
解雇が無効になるということは会社と解雇した社員との雇用契約が終わっていな いと評価されることになります。雇用契約が終わっていないとなると社員は労働者として会社に労務の提供をする義務を追い、一方で会社は社員に対して賃金を支払う義務を追うことになります。賃金は労務提供の対価なわけですから、労務の提供をしない社員に会社は賃金を支払う必要がないというのが原則です。ノーワークノーペイということです。
しかし会社から解雇を言い渡された社員は会社で労務の提供をすることはできず、不当な解雇と評価されますと会社の落ち度で社員が労務の提供をできなくなっていたわけですから、この場合には会社には社員に対する賃金の支払い義務があるということになります。
さらに噛み砕いて説明します。
会社と社員の間には雇用契約が存在します。会社は社員に対して労務の提供を求めることができる「債権者」ということになります。「債権者の責めに帰すべき事由」(不当な解雇)によって「債務」(社員の労務を提供する義務)を履行することができなくなったときは、「債権者」(会社)は、反対給付(労務の提供に対して支払うべき賃金)の履行(支払い)を拒むことができないことになっています(民法第536条2項)。
これが不当解雇の場合には、解雇以降の社員の賃金について会社が支払い義務を追う法的根拠となります。解雇が無効であると裁判所が判断した時点から解雇の時点まで遡って賃金の支払い義務を追うことからバックペイと言われるものです。
(2)バックペイのリスクとそれを超えるリスク
解雇した社員から会社による不当解雇であるとして社員の地位確認を求める法的アクション(労働審判や民事訴訟等)が起こされた場合、社員からの不当解雇であるとの主張が通る形で解決することが多いのですが、民事訴訟であれば解雇の時点から判決が確定する時点又は和解の成立時までに1年以上を要することも珍しくありません。
社員の地位確認が認められる判決が確定しますと職場復帰を認めた上で解雇時から現時点までのバックペイを支払う必要がありますし、職場復帰後にその社員が働けば賃金の支払い義務が発生します。
解雇というリスクの高い手段をとってまで雇用契約を解消したかった社員の職場復帰ということになるとその実害は計り知れません。
このことから解雇をめぐる紛争では会社の解雇が不当であったとの心証が裁判所より示された場合、バックペイは払うのは大前提として将来にわたって発生するはずであった賃金相当額を補填するという意味、不当解雇によって与えた精神的苦痛を慰謝するという意味を持つ解決金を社員に支払って合意退職の形で和解するケースが非常に多いところです。
この解決金の額が賃金の6か月程度で済めば傷は浅い方で1年以上の賃金に相当する解決金を支払わなくてはいけなくなるケースも珍しくありません。
争っている期間のバックペイを支払い、かつ解決金として相応の金額を支払って和解するというのが会社の次善の策(職場復帰よりはましという意味で)であり、解決金の額が高額になるケースも珍しくなく、また裁判に対応する場合には役員や担当の職員が裁判の準備のために時間をとられるという負担、代理人弁護士への着手金・解決後の報酬の負担、裁判の最中「これだけ時間と費用をかけても社員の言い分が通るのではないか、多額の解決金の支払義務が生じるのではないか」との不安を抱え続けなくてはいけないという会社経営者の精神的負担なども考えますと割に合わないことこの上ないということになります。
会社が社員との雇用契約を解消する際に「解雇」という手段を選ぶのは、そのリスクを考えると合理的ではなく、私自身が顧問先企業などから「社員を解雇したい」という相談を受ける際も、仮に解雇が有効になるであろうと予測されるケースであったとしても退職での処理を進めています。
自分が行ったこと等が解雇相当であるという認識を有している社員に対して退職勧奨を行い、退職届を提出していただくなどして退職という形で雇用契約を終了させるハードルは高くありません。
また.退職届を提出した社員から「実は会社に脅されて退職届を書かされたので退職を取り消す」「退職しなくてはいけないという勘違いから退職届を出したので退職を取り消す」などの根拠で法的アクション(民事訴訟や労働審判)が起こされた場合、退職の意思表示を取り消す根拠となっている社員の意思表示が会社の強迫によるものであること等の事実の立証責任は社員にありますので、会社は適切な反論をしていくだけで退職が有効であるとの判断が得られるケースがほとんどだと思います。
また、そもそも退職届を出した社員から退職の意思表示の取り消しを根拠とする地位確認の法的アクションが起こされるケースは、ごくまれです。
第3 退職勧奨が違法になるケースとその結果、会社にもたらされる不利益
退職勧奨については解雇とは異なり、法律上明確な制限があるわけではありませんが、どのような方法を使っても良いわけではありません。
社会的相当性を逸脱した態様での半強制的ないし執拗な退職勧奨行為は、それ自体が不法行為と評価されて、社員に対する損害賠償責任が生じることになります。具体的にどのような退職勧奨行為が不法行為と評価されたかと言いますと
①上司による暴力を伴ういじめが頻繁に繰り返され、無意味な仕事の割当てによる嫌がらせや社員を孤立させる行為が行われたりした事例(東京高判平8・3・27 労判706号69頁)
②社員を孤立させて辞めさせるための長期の嫌がらせが行われた事例(東京地判平14・7・9 労判836号104頁)
③内部告発者に対する退職強要などの言動が許容される限度を超えた侮辱行為にあたると評価された事例(東京地判平30・3・29 労判1184号5頁)
などがあります。
いずれも不法行為と評価されて損害賠償の支払い義務が会社に生じたことになります。
また、違法な退職勧奨によって社員が退職の意思表示をした場合には、その意思表示に瑕疵があるとして意思表示の取消しが認められることがあります。取消しが認められるということは退職していないことになり、雇用契約が存続しているということになりますので不当解雇と同様の問題が生じることになります。
意思表示の取消しが認められたのは以下のようなケースです。
①若い社員を長時間部屋に閉じ込めて懲戒解雇をほのめかして退職を強要した場合には使用者が労働者に畏怖心を生ぜしめて退職の意思表示をさせたと評価されて、強迫による取消しが認められます(松江地益田支判昭44・11・18、東京地判平14・4・9 労判829号56頁)。
②使用者が労働者につき客観的には解雇事由または懲戒解雇事由が存在しないのに、それがあるかのように労働者に誤信させて退職の意思表示をさせたという場合には、錯誤(民法95条)や詐欺(民法96条)が成立しえます
(錯誤を認めたケースとして横浜地川崎支判平16・5・28 労判878号40頁、東京地判平23・3・30 労判1028号5頁、強迫と評価して取消しを認めたケースとして大阪地判昭61・10・17 労判486号83頁)。
第4 退職勧奨を行う方法・手順
1 置かれている現状や会社からの評価を社員に自覚させること
それでは、どのように退職勧奨を行えばよいのでしょうか。
まず、社員に対して会社がどのような評価をしているのかについて正確に理解させることです。会社が退職して欲しい社員に限って自己評価が高く、会社にとって自分が必要不可欠な人材であると考えていたり、問題行動を繰り返していてもこの程度のことは許されると甘い認識を持っていたりします。会社がその社員に対して、会社の期待に十分に応えることができていない、社員のとっている行動について会社は見過ごせるものではないと考えている等、会社の評価を正確に理解させるということです。
能力不足の社員の場合には、会社が社員に期待していること、社員がその期待に添えていない現状があること、どの点において現状に添えていないかという課題の提示、そのためにどこを改善する必要があるのかという会社の考え方を伝える、それに向けて会社が協力できることと社員についても能力を伸ばすために何をすべきかという課題の提示、課題に向けて継続的な指導を行うというプロセスに着手することが重要です。
またパワハラを行う社員については被害申告を踏まえた事実確認、その評価、評価を踏まえた懲戒処分の実施などを行い、自分の行っている行為がパワハラであり許されるものでないことを自覚させるというプロセスを踏みます。
このプロセスの中で社員がとれる選択肢として退職を示すということが考えられます。会社の中で十分に期待に応えられていないという自覚、問題行為を起こしていると
評価されている自覚をもってもらわないと今後の対処を考える(その中で退職も選択肢の1つとして考える)というフローに乗ることはありません。
2 金銭解決の準備
社員が自分の置かれている状況を正確に理解し、退職も視野に入れて考えるようになったとしても退職した後にすぐに就職先が見つかるか、会社を退職した後の生活不安の問題があり、それがネックで退職勧奨が上手くいかないこともあります。
そこで会社としては本来、退職金の支給要件を満たさない社員に対してもある程度の金銭を支払う準備をし、金銭の支払いを条件として提示することも考える必要があります。
前述の解雇という手段を使った場合の経済的なリスクを考えた場合には、ここである程度の金銭の支払いを検討するのは合理的ではないかと思います。
賃料の3か月分くらいが1つの基準で社員側の反応を踏まえて増減を検討するという対応を会社経営者にアドバイスすることが(私自身は)多いです。
なお、1の対応のみで退職に至るケースも少なくありませんので、既に退職の意思を示している社員にこちらから退職金や解決金名目での支払いの提示をする必要はありません。退職勧奨を受けて退職を渋っている社員との関係で交渉をスムーズに進める1つの手段として社員に支払う金銭の準備をして実際の支払いを交渉の材料にしてはいかがでしょうかというのが正確な趣旨になります。
3 会社都合退職での処理の検討
退職勧奨を行い、退職を考え始めた社員が転職先を自分で見つけてきてその後に退職するというケースもありますが(薬剤師や看護師などの専門職ではよくあります)、退職した後に失業給付を受けながら転職先を探すという社員が多いと思います。
そうすると失業給付がどのくらいの期間得られるのかというのが社員の意思決定に重要な影響を与えるケースがあります。
すなわち自己都合退職の場合よりも会社都合退職の場合が失業給付としての基本手当の給付日数が長いことから会社都合退職で処理するという提案をすると退職に向けた意思決定を引き出しやすいという面があるということです。
ただ、会社が助成金をもらっていたりすると特定の期間内に会社都合退職で退職する社員を出すことで支給を受けることができなくなったり支給額を減らされたりすることがありますので助成金をもらってる会社では慎重な対応が必要です。
第5 当事務所のサポート内容
当事務所は主に顧問先企業から社員との雇用契約を解消したいという相談を受けることが多く、その際には退職勧奨をどのようにして行うのかを具体的にアドバイスをしております。
軽率な解雇が会社にもたらす不利益についても正確に理解していただくために、丁寧に説明し、アドバイスに従って退職勧奨を行っていただいた結果、社員が退職したという結果が得られたとの報告を受けることも多いところです。
もちろん顧問契約をいただいていない会社や法人からのスポットでの相談にも対応しておりますし、これまでには、社員との雇用契約の解消についてのスポットでの相談から当事務所と顧問契約を締結していただいた会社、法人も複数ございます。
当事務所では労使問題はもちろん、それ以外の分野においても顧問先企業様からの相談やご依頼に迅速なレスポンスをして、正確で無難な成果物をお届けすることをモットーとしております。「当社には顧問の税理士も社労士もいるけどそろそろ顧問弁護士を依頼する必要があるなぁ。」とお考えの経営者の方は当事務所の顧問契約について気軽にお問い合わせください。
文責 弁護士 浜田 諭