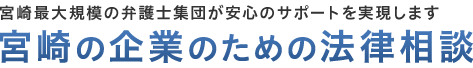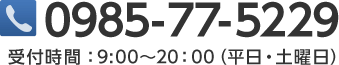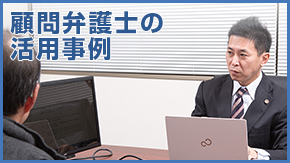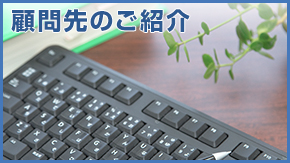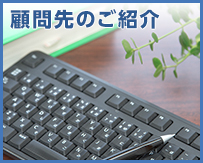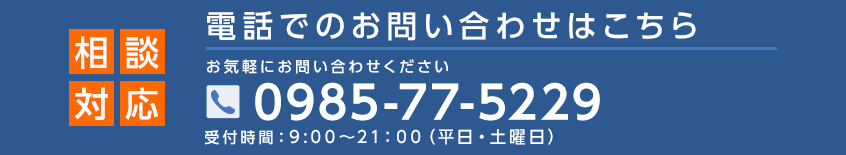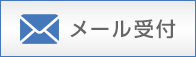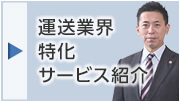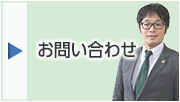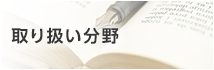懲戒解雇とは?懲戒解雇が認められる場合、認められない場合について、弁護士が解説
今回は顧問先企業から相談を受けることが多いテーマ「解雇の種類-懲戒解雇」についてお話ししていこうと思います。
懲戒解雇のすべて:企業と労働者が知っておくべきリスクとルール
懲戒解雇は、企業が労働者に対して科す最も重い処分であり、労働者の生活とキャリアに甚大な影響を与えます。そのため、企業側にとっては「最終手段」として、労働者側にとっては「絶対に避けたいリスク」として、その規定、要件、そして手続きが厳しく定められています。本コラムでは、懲戒解雇を巡るルールと、実際に起こり得るトラブルについて解説します。
1 懲戒解雇とは
懲戒解雇(ちょうかいかいこ)とは、労働者が企業秩序を乱す重大な非行を行った場合に、その制裁(ペナルティ)として行われる解雇のことです。これは通常の解雇(普通解雇)とは性質が異なり、会社が従業員を「罰する」という側面が強くなります。
企業側は、懲戒解雇を行うことで、他の従業員に対し企業秩序の維持と非行の抑止を図る目的があります。一方で、労働者側から見ると、懲戒解雇は退職金の一部または全部が不支給になることが多く、さらに再就職の際に「懲戒解雇歴」が大きなハンディキャップとなるため、極めて厳しい処分と言えます。
2 懲戒解雇の規定と要件
懲戒解雇を適法に行うためには、いくつかの厳格な要件を満たす必要があります。
(1)懲戒解雇の規定
懲戒解雇を行うには、まず就業規則に懲戒の種類と、どのような場合に懲戒解雇を行うかという懲戒事由が具体的に明記されている必要があります。就業規則に根拠となる規定がない場合、原則として懲戒解雇はできません。
(2)懲戒解雇の要件(労働契約法による規制)
日本の労働法制では、解雇権の濫用を防ぐため、労働契約法第15条により、懲戒解雇を含む懲戒処分には以下の厳しい要件が課されています。
①客観的に合理的な理由の存在
懲戒解雇の原因となった労働者の非行が、社会通念上、解雇するに値するほど重大であるという、客観的な事実が必要です。
②社会通念上の相当性(解雇権濫用の法理)
その非行の性質や態様、労働者のこれまでの勤務状況、会社に与えた損害の程度など、あらゆる事情を考慮して、懲戒解雇という処分が重すぎないか(処分が相当であるか)が厳しく審査されます。
この「相当性」の判断は非常に重要で、たとえ非行があったとしても、いきなり最も重い懲戒解雇を選択することは、相当性を欠くと判断されるリスクが高いです。非行の内容がかなり重大なものでない限り、一般的には、段階的な処分(けん責、減給、出勤停止など)を踏まずに解雇するのは困難とされています。
3 懲戒解雇の流れ
懲戒解雇は、その重大性から慎重な手続きを踏む必要があります。一般的な流れは以下の通りです。
(1)事実調査と証拠収集
非行の事実を正確に確認するため、関係者へのヒアリング、メール、記録などの客観的な証拠を収集します。この段階で、労働者本人からの弁明の聴取は必須です。
(2)就業規則との照合と処分の検討
収集した事実が就業規則のどの懲戒事由に該当するかを確認し、非行の重大性や過去の判例などを参考に、懲戒解雇の相当性を慎重に検討します。
(3)懲罰委員会の開催(就業規則上懲戒委員会の規定があれば)
会社によっては、公平な処分決定のため、懲罰委員会などの機関を設け、そこで処分案を審議します。
(4)懲戒解雇の決定と通知
懲戒解雇を決定した場合、労働者に対し、解雇の理由を明記した書面をもって通知します。
(5)解雇予告手当の支払いまたは解雇予告
懲戒解雇の場合も普通解雇と同様、原則として解雇予告(30日前)または解雇予告手当の支払いが必要です。ただし、労働基準監督署長から「解雇予告除外認定」を受けた場合は、予告・手当なしで即時解雇が可能です。この認定は、非行が極めて悪質で「労働者の責に帰すべき事由」に該当する場合に限られ、手続きには時間がかかります。
4 懲戒解雇でよくあるトラブル事例
懲戒解雇は、しばしば裁判や労働審判に発展します。特にトラブルになりやすいのは、以下の点です。
(1)証拠の不備・事実誤認(懲戒対象事実が認定されないケース)
企業側が十分な調査を行わず、「噂」や「推測」に基づいて解雇した場合、非行の事実認定が覆り、解雇が無効となるケースが多発します。
(2)処分が重すぎる(相当性の欠如)
遅刻・欠勤が続いたケースや、軽微な業務命令違反など、非行の程度が比較的軽いにもかかわらず、いきなり懲戒解雇を行った場合、「処分が重すぎる」として無効になることが非常に多いです。過去の事例では、金銭的な横領などの重大な非行でも、長年の功績や反省の態度によって解雇が無効になった例もあります。
(3)手続き上の瑕疵
就業規則の懲戒規定を社員に周知していなかったり、懲戒処分を行う際に本人に弁明の機会を与えなかったりといった手続き上の不備があった場合、解雇の実体的な理由の有無にかかわらず、懲戒解雇が無効とされるリスクがあります。
5 懲戒解雇が認められる場合・認められない場合
裁判例に基づき、懲戒解雇が有効になりやすい事由と、無効になりやすい事由を解説します。
(1)懲戒解雇が認められる(有効になりやすい)場合
①重大な犯罪行為
会社内での窃盗、横領、暴行などの刑法犯に該当する行為。
②機密情報の漏洩
企業の死活問題に関わる営業秘密などを、故意または重大な過失で外部に漏洩し、会社に甚大な損害を与えた場合。
③度重なる虚偽報告・詐称
経歴詐称、不正な残業代請求など、会社との信頼関係を根本から破壊する行為。
④極めて悪質なハラスメント
複数回にわたるセクハラやパワハラなど、他の従業員の就業環境を著しく悪化させた場合。不同意性交罪、強制わいせつ罪に該当する行為があった場合には懲戒解雇が有効とされるケースが多いです。
(2)懲戒解雇が認められない(無効になる)場合
①軽微な私生活上の非行
業務に関係のない私的な飲酒運転や犯罪行為であっても、会社に直接的な損害や信用の失墜がないと判断される場合。
②偶発的・軽微なミス
1度や2度の遅刻、業務上の軽微なミス、指示内容の小さな誤解など。
指導・注意を欠いた場合: 会社が改善の機会を与えることなく、いきなり懲戒解雇に踏み切った場合。
③非行と処分のバランスを欠く場合
たとえば数千円程度の経費の私的利用に対し、即座に懲戒解雇を下した場合など。
懲戒解雇は、非行の事実と処分としての相当性の両方が揃って初めて有効となります。少しでも相当性に疑問符がつく場合は、無効になるリスクが高いと認識すべきです。
6 懲戒解雇に関して弁護士に相談するメリット
懲戒解雇は、法的な要件が厳しく、トラブルになった場合の影響が非常に大きいため、企業・労働者双方にとって弁護士への相談が不可欠です。
企業が弁護士に相談するメリットとしては以下のものが挙げられます。
(1)手続きの適法性確保
懲戒解雇の手続き(事実調査、弁明機会の付与など)が法的に問題ないかを確認し、後の訴訟リスクを最小限に抑えられます。
(2)処分の相当性判断
懲戒事由の重大性に基づき、懲戒解雇が有効となるか、またはどのような処分(諭旨解雇、普通解雇など)が適切か、過去の判例から具体的なアドバイスが得られます。
(3)労働基準監督署への対応
解雇予告除外認定申請など、行政手続きのサポートを受けられます。
7.当事務所のサポート内容
当事務所は多くの会社の顧問業務を日常的に行っており,その中で懲戒解雇についての相談を受けるケースも少なくありません。また懲戒解雇、普通解雇に限らず顧問業務の中で問題社員との雇用契約終了に向けてのアドバイス,退職勧奨の方法等についての助言、雇用契約終了について紛争化した場合の会社の代理人としての交渉対応,訴訟対応などを行っております。
社員との雇用契約終了(解雇,退職等)に向けて弁護士から適切な助言を得るには,紛争化した後のスポットでの対応を依頼するよりも,日頃から問題社員対応について弁護士から助言を得られる体制作りをされること(顧問弁護士を依頼されること),顧問弁護士に問題社員対応等を相談することを習慣にされることをお勧めします。このことにより会社の業務や社内での人間関係を理解した上での助言を顧問弁護士から得ることが可能となるからです。
当事務所との顧問契約を検討されたい会社経営者の皆様,人事担当者の皆様は遠慮なくお問い合わせください。
- 円満退職を叶える退職勧奨のポイント|企業法務に詳しい弁護士が解説
- 債権回収を弁護士に依頼するメリットと判断基準について解説
- 既に退職した社員から現場への直行直帰を伴う就労について現場への移動時間、現場からの戻り時間についても労働時間であり、この時間について賃金が支払われていないことを理由に未払い賃金を請求されたものの元社員の請求額を大幅に削った内容の判決から付加金を削った内容にて控訴審が判決を下し、これが確定して解決した事例
- 懲戒解雇とは?懲戒解雇が認められる場合、認められない場合について、弁護士が解説
- 【ご報告】代表弁護士柏田笙磨が国際ロータリー第2730地区の危機管理委員(弁護士)に選任されました
- 解雇の種類と注意すべきポイントを弁護士が解説
- 問題社員について解雇するのではなく交渉によって会社都合退職という形で合意退職による解決ができた事例
- 遅刻や欠勤を繰り返す問題社員を放置するリスクとは?企業が知っておくべき対応方法について弁護士が解説
- 業務の指示に従わない社員にどう対応する?問題社員対応について弁護士が解説
- 非違行為のある社員とは?企業の適切な対応方法について弁護士が解説