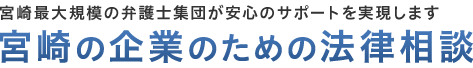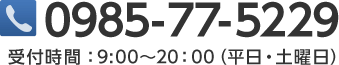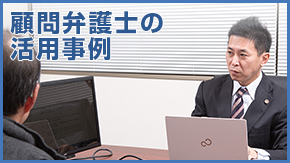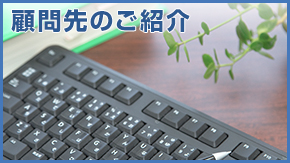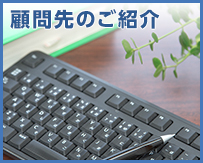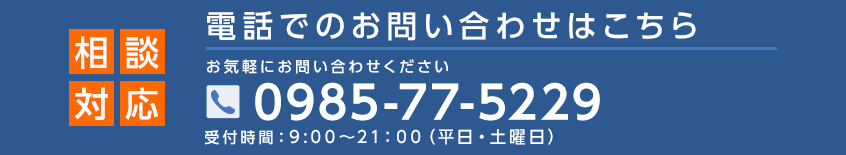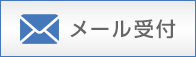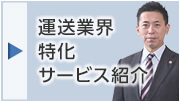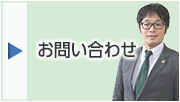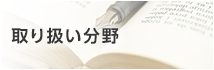解雇の種類と注意すべきポイントを弁護士が解説
今回は顧問先企業から相談を受けることが多いテーマ「解雇の種類と注意すべきポイント」についてお話ししていこうと思います。
お話しする内容は以下のとおりです。
1 解雇に関して会社側からのよくある相談とそれに対する回答
2 解雇の種類
(1)普通解雇
(2)懲戒解雇
(3)諭旨解雇
(4)整理解雇
3 解雇を行う際に注意すべきポイント
4 解雇に関して弁護士に相談するメリット
5 当事務所のサポート内容
1. 解雇に関して会社側からのよくある相談とそれに対する回答
(1)勤務態度が悪い従業員を辞めさせたいが,解雇に向けてどのように進めればよいか?
勤務態度の悪さを理由とする解雇は解雇無効となるリスクが高いので退職勧奨を先行させて可能な限り退職で処理しましょう。
(2)不祥事を起こした従業員を懲戒解雇したいが,解雇予告手当を支払わずに済む方法があると聞いた。どのように進めればよいか?
解雇予告除外認定申請を労基署に提出して除外認定を受けることができれば解雇予告手当を支払わずに済みますが,懲戒解雇相当の社員についても退職で処理する方が良いケースが多いので(懲戒解雇が無効となるケースが多いので)まずは退職勧奨をしてみましょう。
懲戒解雇の場合には退職金を支給しないとの退職金規定があり,この規定に基づいて処理したいとの希望がある場合には懲戒解雇,解雇予告除外認定という方法をとっても構いません。なお懲戒解雇が有効である場合でも退職金全額を支給しないで済むケースは限定的ですのでその点はご注意ください。
(3)問題行動の多い社員を解雇したところ,解雇予告手当を支払っているにも関わらず解雇が無効であるとの文書が届いたがどうしてか?
解雇予告手当は解雇するにあたっての手続として要求されているだけで支払えば不当解雇にならなくなるというものではありません。解雇は,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない場合は,その権利を濫用したものとして無効(労働契約法16条)となりますが,解雇予告手当を支払っているかどうかは解雇権濫用として無効と評価されるかどうかと直接関係ありません。
2. 解雇の種類
解雇には,主に以下の4種類があります。
(1) 普通解雇
労働者の能力不足や規律違反など,労働者側に原因がある場合に行われる解雇です。具体的には,以下のようなケースが挙げられます。
・業務命令に従わない
・協調性がない
・職務上の成績が著しく悪い
(2) 懲戒解雇
就業規則に定められた懲戒事由に該当する重大な規律違反があった場合に行われる,最も重い処分の解雇です。以下のような行為が懲戒事由に該当します。
・会社の資金を横領した
・無断欠勤が長期間続く
・重大な経歴詐称があった
(3) 諭旨解雇
懲戒解雇に値するほどの重大な規律違反があったが,本人の反省や情状酌量の余地がある場合,懲戒解雇ではなく,自主的な退職を促すものです。諭旨解雇の場合,退職金の一部または全部が支給されることがあります。
自主的な退職に応じない場合は懲戒解雇に処するという取り扱いをする企業が多いです。
(4) 整理解雇
会社の経営悪化や事業縮小など,会社側の都合で行われる解雇です。整理解雇を行うためには,以下の4つの要素が考慮されます。以前はこの4つが全て揃うのが要件であるという考え方をとる裁判例が多かったですが,現在ではこの4つは判断要素であるという考え方に立つ裁判例が主流となってきています。
①人員削減の必要性:本当に人員削減が必要な状況か
②解雇回避努力義務の履行:希望退職者の募集や配置転換など,解雇を回避するための努力を尽くしたか
③被解雇者選定の合理性:解雇する人の選び方に客観的・合理的な基準があるか
④手続きの妥当性:労働組合や労働者に対して,十分に説明・協議を行ったか
3. 解雇を行う際に注意すべきポイント
会社が解雇を行う際には,以下の点に細心の注意を払う必要があります。
(1)正当な理由の存在:客観的に見て合理的な理由がなければ,不当解雇と判断されます。
普通解雇をする場合には,この点を慎重に判断する必要があり,基本的には解雇という手段ではなく退職勧奨から自己都合退職で処理するというのが最適解となります。
解雇はあくまでも最終手段であり,その際には不当解雇と評価された場合のリスクと即時解雇をするメリットを比較考量してメリットが明らかに上回るケースについてだけ解雇という手段が妥当になると考えますし,そのようなケースはほとんど考えられません。
懲戒解雇をする場合にも懲戒相当な事実がまず存在するかどうかが重要となりますし,そもそもこの事実が客観証拠で裏付けられない場合には懲戒処分をするかどうかについても慎重な判断が必要となりますし,懲戒解雇という手段をとることは基本的に妥当ではありません。
(2)懲戒解雇という手段が適切かどうか
社員が懲戒相当の行為をしているとしても,その行為と懲戒解雇という手段のバランスがとれていなければ懲戒解雇は無効となります。例えば1回の軽微な不祥事で懲戒解雇をするというのが懲戒対象行為に比して懲戒解雇という手段が重すぎるという話になり,懲戒解雇は無効となりますので注意が必要です。
(3)手続きの履行
解雇の場合には解雇予告手当の支払いが必要になりますし,懲戒解雇の場合には懲戒処分に先行して対象者に弁明の機会を与えることが必要となります。懲戒解雇の場合には,この手続の履行を怠ること自体が懲戒解雇無効という判断につながることがあり,注意が必要です。
(4)4要素の検討と4要素を満たすような対応
整理解雇の場合には前述の4要素を満たす整理解雇となっているのかどうかを検討して4要素を満たす実態を整えて解雇する必要があります。
そもそも人員削減の必要がなければ整理解雇自体が無理ですし,整理解雇が有効と評価されるためには解雇回避努力,解雇対象者の選定をきちんと行い,労働組合や労働者に対して十分に説明・協議を行う必要があります。
4. 解雇に関して弁護士に相談するメリット
解雇に関して弁護士に相談するメリットは,以下の通りです。
(1)法的な助言を得られる
そもそも問題社員等への対応として解雇という手段が適切かどうかの判断を聞くことができますし,解雇せずに目的を達成できてリスクが少ない退職の方向で対応するノウハウ(退職勧奨の進め方等)を教えてもらうことが可能です。特に労使紛争を多く扱っている弁護士に相談することで雇用契約の終了に向けた適切な法的アドバイスを得るメリットはかなり大きいものがあります。
また最終的に解雇する場合にも解雇に向けた準備をどのように進めていけばよいのか,解雇した場合に生じるであろうリスクを事前に評価してもらうことが可能です。
(2)紛争になる前,紛争になった場合の代理人としての対応
社員との退職勧奨や解雇に先行した退職条件の交渉について会社側の代理人として弁護士に依頼することで会社にとって有利な条件で合意退職での解決ができるケースが少なくありません。
紛争状態になった場合には弁護士に会社の代理人として交渉業務をしてもらうことで社員との直接交渉を行うことによる時間や労力,精神的な負担の軽減につながることが多いです。
訴訟や労働審判に発展した場合には弁護士に会社の代理人に立ってもらうことで法的紛争の解決に向けて有益な助言を得ながら,専門性の高い文書を作成する作業を弁護士が作成する形となり,紛争状態の渦中に巻き込まれて経営者・人事担当者が直接対応する様々なコストを軽減することが可能です。
また会社が代理人として弁護士を立てることで,適切な法的主張をできないまま社員側の不当な要求を裁判所が認めるリスクを軽減することができ,紛争から被る会社の被害を最小限にすることができます。
5.当事務所のサポート内容
当事務所は多くの会社の顧問業務を日常的に行っており,顧問業務の中で問題社員との雇用契約終了に向けてのアドバイス,退職勧奨の方法等についての助言,解雇に向けた社内対応についての助言,雇用契約終了について紛争化した場合の会社の代理人としての交渉対応,訴訟対応などを行っております。
社員との雇用契約終了(解雇,退職等)に向けて弁護士から適切な助言を得るには,紛争化した後のスポットでの対応を依頼するよりも,日頃から問題社員対応について弁護士から助言を得られる体制作りをされること(顧問弁護士を依頼されること),顧問弁護士に問題社員対応等を相談することを習慣にされることをお勧めします。このことにより会社の業務や社内での人間関係を理解した上での助言を顧問弁護士から得ることが可能となるからです。
当事務所との顧問契約を検討されたい会社経営者の皆様,人事担当者の皆様は遠慮なくお問い合わせください。
- 円満退職を叶える退職勧奨のポイント|企業法務に詳しい弁護士が解説
- 債権回収を弁護士に依頼するメリットと判断基準について解説
- 既に退職した社員から現場への直行直帰を伴う就労について現場への移動時間、現場からの戻り時間についても労働時間であり、この時間について賃金が支払われていないことを理由に未払い賃金を請求されたものの元社員の請求額を大幅に削った内容の判決から付加金を削った内容にて控訴審が判決を下し、これが確定して解決した事例
- 懲戒解雇とは?懲戒解雇が認められる場合、認められない場合について、弁護士が解説
- 【ご報告】代表弁護士柏田笙磨が国際ロータリー第2730地区の危機管理委員(弁護士)に選任されました
- 解雇の種類と注意すべきポイントを弁護士が解説
- 問題社員について解雇するのではなく交渉によって会社都合退職という形で合意退職による解決ができた事例
- 遅刻や欠勤を繰り返す問題社員を放置するリスクとは?企業が知っておくべき対応方法について弁護士が解説
- 業務の指示に従わない社員にどう対応する?問題社員対応について弁護士が解説
- 非違行為のある社員とは?企業の適切な対応方法について弁護士が解説