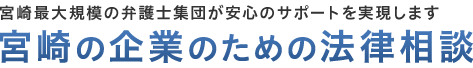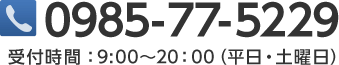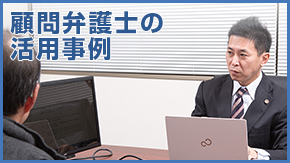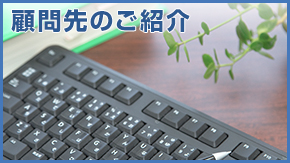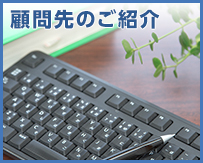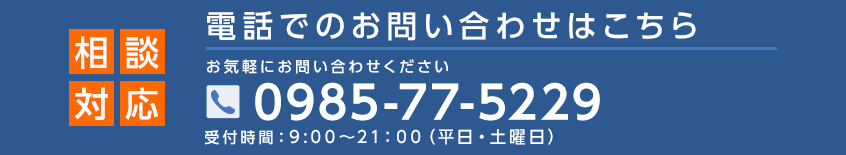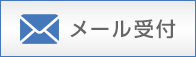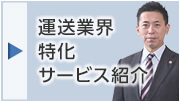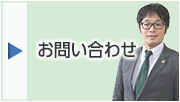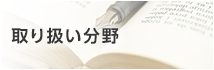建設業における労働組合との団体交渉について|企業法務に詳しい弁護士が解説
今回は建設業における労働組合との団体交渉についてお話していこうかと思います。
お話しする項目は以下のとおりです。
1 建設業における団体交渉の特徴
2 団体交渉に発展してしまった場合の企業の対処方法
(1) 団体交渉の対応のポイント
(2) 団体交渉を拒否できるケース
3 団体交渉の対応時にやってはいけないこと
4 団体交渉対応時に弁護士に依頼すべき理由
5 当事務所がサポートできること
1 建設業における団体交渉の特徴
建設業において発生しやすい個別労使紛争が団体交渉で取り上げられる傾向にあると思います。
労働時間管理の難しさから労使において労働時間の評価をめぐる争いが生じやすい未払い賃金請求,ハラスメントをめぐる問題が団体交渉で取り上げられやすいと感じています。
建設業に限らず中小企業においては社内に労働組合が結成されていないケースが多いので社内労組単体で団体交渉の申し入れをするケースはまれであり,社員が社外の合同労組・ユニオンに加入して,これらの労組から申し入れがあるケースが多く,社内労組が結成されても社外の合同労組・ユニオンと連名で団体交渉を申し入れてくることもあります。
2 団体交渉に発展してしまった場合の企業の対処方法
(1) 団体交渉の対応のポイント
対応のポイントを考えるにあたっては,労働組合とは何であるのか,労働組合や組合員を守っている法律「労働組合法」について理解しておく必要があります。
労働組合は,「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体」(労働組合法2条本文)のことです。
日本国憲法は,労働者に「団結権」,「団体交渉権」,「団体行動権」の労働三権を保障していますが(憲法28条).「団結権」は,労働組合の結成・運営をすることを保障する権利です。「団体交渉権」は,労働者が使用者と団体交渉を行うことを保障する権利であり,「団体交渉」とは労働者がその代表者を通じて,使用者やその団体と労働条件その他の待遇や労使関係上のルールについて交渉を行うことを指します。
「団体行動権」は,争議権と組合活動権を総称したものであり,争議権は正当性のある範囲での争議行為(ストライキ,ピケ,ボイコット)の法的保障を内容とする権利,組合活動権とは,正当な範囲でビラ配り,デモ,集会などの法的保障を内容とする権利になります。
労働三権があることから,労働組合の結成・運営や団体行動について刑事責任・民事責任の免責効果が生じ,労働組合上の不当労働行為の救済制度が設置され,労働三権を侵害するような行為は無効になり違法と評価されるという効果も発生します。
この点は必要に応じて後述します。
労働者が団結して団体交渉をすることを保障するために使用者の解雇権,人事権,雇用契約締結の自由を制限しており,これらは「不当労働行為」として類型化されています。
不当労働行為にはどのようなものがあるのでしょうか。
① 不利益取扱いの禁止
労働者が労働組合の組合員であること,労働組合に加入したこと,これを結成しようとしたこと,労働組合の正当な行為をしようとしたこと等を理由として,その労働者を解雇したり,それ以外の不利益な取り扱いをすることは禁止されます。
その場面は多岐にわたり,労働者に不利益な配置転換・出向,給与・手当・退職金の支給等,あらゆる場面で機能しますので要注意です。
また労働者が労働組合に加入しないこと,脱退することを雇用条件とすることも禁止されます。
② 団体交渉の拒否
使用者が労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由なく拒否することは禁止されます。団体交渉自体を拒否すること自体はもちろん,団体交渉において不誠実な態度をとることも禁止されますので注意が必要です。
③ 支配介入の禁止
労働者が労働組合を結成し,運営することを支配したり,これに介入したりすることは禁止されています。例えば組合員に対して脱退を勧誘したり,従業員へ不加入の勧誘をしたりすることがこれに当たります。
また労働組合の運営のための経費の支払いについて,経理上の援助をすることも禁止されます。一見,利益を与えているので良いことのように思えますが,経理上の援助を与えることによって労働組合に対して影響力を持つことがあり得ますので,このような援助も支配介入に当たるとして禁止されているものです。
(2)団体交渉を拒否できるケース
団体交渉は正当な理由があれば拒否することができますが,正当な理由なく拒否すると団体交渉拒否という不当労働行為(労働組合法7条2号)にあたることになりますので慎重に判断する必要があります。
① 労働者性・使用者性
請負労働者や派遣労働者を受け入れて業務を行っている会社は多いですし,特に建設業においては受け入れているところが多いと思います。
請負労働者については以下の判例(朝日放送事件 最高裁 平成7年2月28日判決)があり,これが参考になります。
「事業主が雇用主との間の請負契約により派遣を受けている労働者をその業務に従事させている場合において,労働者が従事すべき業務全般につき,作業日時,作業時間,作業場所,作業内容等その細部に至るまで事業主が自ら決定し,労働者が事業主の作業秩序に組み込まれていて,事業主の従業員と共に作業に従事し,その作業の進行がすべて事業主の指揮監督の下に置かれているなど判示の事実関係の下においては,事業主は,労働者の基本的な労働条件等について雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配,決定できる地位にあり,その限りにおいて,労働組合法7条にいう「使用者」にあたる。」
この判例が想定しているような請負労働者について自社が雇用していないから(自社が「使用者」でないから)といって団体交渉を拒否することはできないことになります。派遣労働者との関係では労働時間,休憩などの労基法上の責任,作業時間の制限といった労働安全衛生法上の責任,ハラスメント防止義務などは派遣先にも適用されますので,派遣先は団体交渉に応じる義務があります。すなわち団体交渉を拒否すると不当労働行為に当たることになりますので注意が必要です。
② 解雇した労働者・退職した労働者の労働者性
解雇や退職の効力を争っている者は,労働組合法7条2号の労働者に該当するとの裁判例が多いですし(例えば日本鋼管鶴見造船所事件 東京高裁昭和57年10月7日判決),実務上は労働者に当たるという前提で団体交渉に応じるのが通例です。
解雇した後にその効力を争わずに未払い賃金や退職金のみを争っている場合についても労働組合法7条2号の「労働者」に当たるとして団体交渉に応じるのが通例であり,「労働者」に当たるとした裁判例もあります(松浦塩業組合事件 高松地裁丸亀支部昭和34年10月26日判決)。
③ 管理職であること
職場の管理職は,労働組合員になれないとして管理職からの団体交渉を拒否できるのかという問題がありますが,労働組合法が組合員の範囲から外している労働者は以下のような限定的な者であり,ほとんどのケースでは管理職であることを理由とした団体交渉拒否は正当化されません。
例外的な場合は「役員、雇入解雇昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者、使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接にてい触する監督的地位にある労働者その他使用者の利益を代表する者」(労働組合法 2条本文 但書・1号)ですが,このような立場の人が労働組合に加入して団体交渉をしてくることは通常想定されませんので「管理職」であることを理由として団体交渉を拒否できる場面はほとんどないと考えておきましょう。
④ 組合員名簿・組合規約の不提出
特に合同労組の場合には,組合員名簿や組合規約の提出を求めて,その提出に応じるまでは団体交渉に応じないというスタンスをとる会社経営者もいるようですが,組合員名簿の提出が労働組合側の要求との関係で合理的に必要な場合(通常はあまり考えられません)でない限りは団体交渉を拒否する正当な理由にはなりません。
3 団体交渉対応時にやってはいけないこと
(1)組合結成通知,団体交渉申入れ書を受け取ったら(初動)
団体交渉申入れ書に団体交渉の日時が書いてあっても,その日時に団体交渉に応じる必要はありません。準備不足で団体交渉に及ぶことによってその後の団体交渉が労働組合主導で展開する可能性もありますし,団体交渉時に会社に不利な発言を引き出されて労働組合から集中砲火を浴びるリスクもあります。
そこでまずは回答猶予を求める連絡文書を出して,団体交渉に向けた準備を進めるべきです。この段階で会社として対応していくのか代理人弁護士を立てて窓口とするのかを検討してもよいと思います。
ここで会社側が代理人弁護士を立てた場合には窓口を一元化すべきであり,それ以降,労働組合との間では弁護士を通さないやり取りをしてはいけません。
(2)回答書の送付と団体交渉日時等の調整
労働組合に対して回答猶予を申し入れる連絡文書を出してから内容のある回答を出すまでに時間をかけてはいけません。団体交渉を拒否していると評価されるリスクがあるからです。例えば令和7年4月15日までに回答しますとの文書を事前に送っている場合は同日までに到達するように回答書を送付する必要があります。
会社から労働組合に回答書を送付する際には,労働組合から申し入れがあった内容について中身のある回答をすることになるのですが,申し入れられた内容について不明確なところがある場合には趣旨を明確にして欲しい旨の質問をしても構いません。
この回答と同時,または並行して会社側から団体交渉の候補日時,場所,出席者,議題を記載した文書を労働組合に送付して団体交渉の場を設定する努力をしましょう。
労働組合から提案があるものに回答をするという「受け」のスタンスで臨むのではなく,会社が団体交渉に応じる姿勢を示す,団体交渉の場の設定について主導権をとるという意味で「攻め」の姿勢で対応していくのが良いと考えます。
団体交渉の日時・場所等の設定について何点か注意をしておきます。
時間については労働者の就労が終わった後すなわち所定就業時間よりも後に設定することです。所定就業時間内に団体交渉を行う場合には,団体交渉に参加するために就業しなかった労働者をどう処遇するのかという問題が生じるからです。有休を消化させるという手段も欠勤控除をするという手段も不適切であり,一方で他の社員が就労している間に団体交渉のために欠勤している社員だけ通常通りの賃金を支払うのも非組合員である社員との間で不公平が生じるでしょう。
「場所」についてですが,会社の会議室や組合の事務所ではなく,社外の施設を利用して行うことをお勧めします。団体交渉について終わりの時間が決まっていないと延々とその場で結論が出ることがない問題について議論をすることになったり,会社側がエンドレスな交渉に嫌気がさして譲歩した方が楽であるという心理状態に追い込まれる危険が生じるからです。会社が社外の会議室を借りてその会場代は会社が支払うというのが最も無難であると考えます。
「出席者」についてですが,総務部長など会社の事情を知っているものの会社の意思決定をする権限がない人とその部下などがいいのではないかと思います。会社の社長が出席するとその場で意思決定を迫られるリスクがあり,一方で会社の内情を知らない人,それなりの立場がない人を形だけ出席させるという対応をすると団体交渉に誠実に応じていないとして不当労働行為に当たると評価される危険があるからです。
また顧問社労士の立会いについてですが,弁護士法72条との関係で「代理人」としての立場ではないというスタンスでの同席であれば問題ないのではないかと考えます。
代理人弁護士の立会いについては,問題ないと考えますし,使用者側代理人としての経験が豊富な弁護士の立会いによって団体交渉の場が荒れるのを予防できたり,議論がかみ合っていない際の交通整理をしてもらえるという期待も持てます。
(3) 団体交渉の事前準備
団体交渉当日までに会社側がどこまでを交渉当日に回答するか,どのような回答をするか,労働組合側の申入れの趣旨が不明確なものについてどのような対応をするのか(事前に質問の趣旨が明確になっていない場合)等について弁護士,社労士に相談して準備をしておくことです。
また団体交渉当日は交渉開始予定時間よりも早めに会場に入って会場の入り口側に席をとって労働組合側の出席者が来るのを待つことをお勧めします。現在の団体交渉においてそこまで荒れた展開になることはほとんどないと思いますが,交渉の場が荒れて収拾がつかなくなった際に退席しやすい場所に着席しておく方が無難という意味で入口側の席をとることをお勧めする次第です。
(4)団体交渉当日について
労使双方の出席者の紹介から始まって,労働組合側から交渉事項の説明があり,それに対して会社側が回答して,それについて質疑応答が行われるというのが通常の団体交渉の手順になると思います。
交渉当日は事前に弁護士や社労士に相談して当日の回答予定内容を共有し,ここまでは回答するが,ここから先は回答しない,次回までに検討して回答するというスタンスを決定しておくことです。
事実関係に争いがある点について会社側が一方的に悪いというスタンスでの質問があったとしても冷静に回答し,その場で回答できないものはその旨を伝えることです。
労使の関係で意見対立や紛争が顕在化しているからこそ団体交渉が行われるわけですが,
意見対立の解消や紛争の解決は双方にとって共通の利害だと思いますので交渉を行うからには双方が率直な意見を述べて,内容のあるやり取りができるように心がけましょう。
労働組合側がヒートアップしても会社側は落ち着いて対応することです。
4 弁護士に依頼すべき理由
会社が単独で団体交渉に対応することが難しいケースが多いと感じています。通常の交渉とは異なり,前述のように不当労働行為の規定があることで守られている労働組合との交渉は「無視する」「不満であれば訴訟でも労働審判でもしてくれ」といった対応をすることができないという縛りがあること,一方で労働組合の言いなりになる必要はなく会社は自らの主張や意見をきちんと主張していく必要があるという面があることから「交渉」の専門家である弁護士に交渉の場の設定,交渉の場でのやり取りについてサポートを得る方が良いと考えます。
弁護士であればどの弁護士でも良いというものではなく労使紛争に関わった経験が多く会社側のスタンスに立ちつつも落としどころを探ることができる柔軟性を有している弁護士に代理人を依頼することをお勧めします。
5 当事務所に依頼するメリット
当事務所は建設業を含む100社以上の顧問先からの相談やその依頼に基づく事件処理を日常的に行っており,労使紛争を始めとする紛争の交渉段階,交渉が決裂した場合の裁判等の法的手続きにおいても豊富な経験と実績を有しております。
労働組合からの団体交渉についても対応実績があり,その点でも労組対応で困っておられる会社,法人のお役に立てると思います。
また,顧問先以外の法人,個人事業主からのスポットでの相談や案件対応についても行っております。建設業を営んでおられる会社,個人事業主の方からの相談や案件対応の依頼も少なくありません。
労働組合からの団体交渉への対応はもちろん,労働者への対応にお困りの建設業を始めとする会社経営者,個人事業主の皆様,当事務所へのご相談,ご依頼を検討されてはいかがでしょうか。

文責 弁護士 浜田 諭