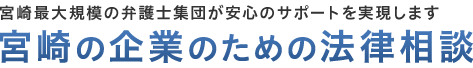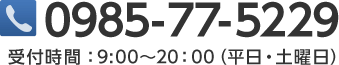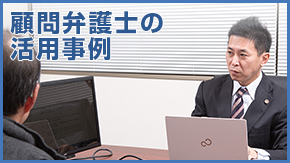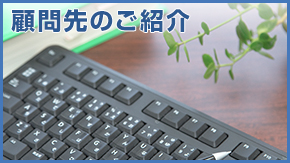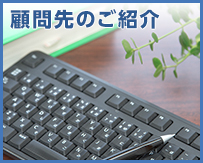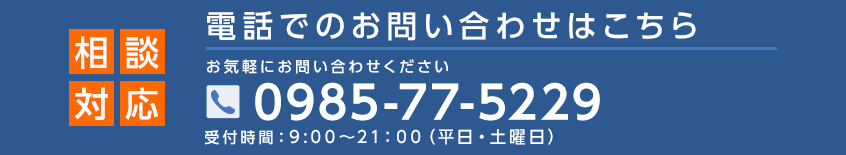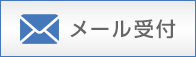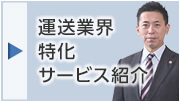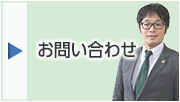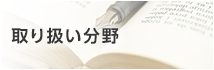保育園・幼稚園を運営する法人の経営者の皆様へ
幼稚園・保育園における法律相談・トラブルとその対策
幼稚園や保育園は、子どもたちの健やかな成長を支える重要な役割を担っています。しかし、その運営においては、様々な法律問題やトラブルに直面することが少なくありません。ここでは、幼稚園・保育園からのよくある法律相談・トラブル事例を挙げ、それらを未然に防ぐためのポイント、そして弁護士に相談するメリットについて解説します。
1. 幼稚園・保育園からのよくある法律相談・トラブル
幼稚園や保育園で起こりやすいトラブルは、大きく分けて以下の5つのカテゴリーに分類できます。このようなトラブルについて顧問弁護士に定期的に相談する必要についても少し触れておきます。
(1)労務問題
職員の働き方や待遇に関する問題は、幼稚園・保育園で最も多く発生するトラブルの一つです。
①残業代の未払い―労働時間の管理
特に、朝早くから夜遅くまで園児を預かる施設では、職員の労働時間が長時間になりがちです。適切な労働時間管理や残業代の計算・支払いがなされていない場合、職員からの残業代請求や職員等からの申告に基づく労働基準監督署からの是正勧告につながることがあります。
②ハラスメント(パワハラ・セクハラなど)
職員間や上司から部下へのハラスメントも深刻な問題です。ハラスメントは、職員の精神的な負担を増大させ、離職の原因となるだけでなく、園の評判にも影響を及ぼします。
幼稚園の教諭や保育士の間では長いキャリアを持ったベテランと新人との間で経験や能力の差が大きいことも少なくなく,ベテランから若手への指導がパワハラ的と評価されるケースも見受けられます。業務上の指導として適切なものであったとしても若手からパワハラだと主張された結果、ベテランが委縮して適切な教育・指導がしづらくなるということもあり、この点にも配慮が必要です。
③不当解雇・退職勧奨
職員の能力不足や規律違反を理由に雇用契約を解消する場合に不用意に解雇をしてしまうと不当解雇と評価されて、労働審判や民事訴訟に発展する可能性があり、ほとんどのケースで多額の金員を支払う形での厳しい解決になることが多いです。この観点から退職勧奨を利用するのが最適解であることが多いのですが、退職勧奨もその方法によってはハラスメントとみなされるリスクがありますので注意が必要です。
④給与・賞与・退職金に関するトラブル
就業規則や雇用契約に基づかない給与の減額、賞与の不支給、退職金の計算ミスなどは、職員との信頼関係を損ね、トラブルに発展しやすい問題です。
⑤有給休暇・育児休業・介護休業の取得
職員がこれらの権利を適切に行使できない場合、労働基準法や育児介護休業法違反となる可能性があります。特に、人手不足の園では、職員の希望通りの取得が難しいケースもあり、トラブルにつながることがあります。
(2) 保護者対応(カスタマーハラスメント又はそれに近いもの)
保護者からのクレームは、時に度を超し、職員の精神的負担となるカスタマーハラスメントに近い状況を生み出すことがあります。
①過度な要求・クレーム
「〇〇をさせろ」「△△はできないのか」といった過度な要求や、些細なことに対する執拗なクレーム、一方的な誹謗中傷などが挙げられます。このような要求に対応する幼稚園教諭や保育士には大きい精神的な負担が生じますので、不当な要求には応じず職員をきちんと
守るという姿勢が重要となります。
②誹謗中傷・SNSでの拡散
園や職員に対する不満をSNSに書き込み、拡散することで、園の評判を著しく低下させるケースがあります。根拠のない誹謗中傷は、保育士個人への名誉毀損や園に対する業務妨害に該当する可能性もあります。度を越えた誹謗中傷等には毅然とした対応が必要となります。
③長時間にわたる電話や面談の要求
保護者が長時間にわたる電話での説明や、必要以上の面談を繰り返し要求することで、職員の業務に支障をきたし、精神的に追い詰めることがあります。
④園の方針への不当な介入
園の教育方針や保育内容に対して、個別の要望を強く主張し、他の園児や職員に影響を及ぼすようなケースです。
⑤保育料等の支払いに関するトラブル
保育料や給食費の滞納、教材費などの支払いをめぐるトラブルも少なくありません。
(3)不適切保育
不適切保育は、子どもの心身に悪影響を及ぼす行為であり、社会的な関心も高く、発覚した場合には園の存続にも関わる重大な問題です。
①身体的・精神的な虐待
園児を叩く、殴る、蹴るなどの身体的な暴力や、大声で叱責する、無視する、威圧的な態度をとるなどの精神的な暴力が含まれます。
②ネグレクト(育児放棄)
必要な食事を与えない、適切な衣類を着させない、衛生状態を保たないなど、子どもの基本的なニーズを満たさない行為です。
③言葉の暴力・差別
特定の園児に対する差別的な発言、侮辱的な言葉、からかいなどが含まれます。
④性的な不適切行為
子どもに対するわいせつな行為や言動、性的な写真を撮るなどが該当します。
⑤発達段階に合わない関わり
子どもの発達段階を無視した過度な期待や、一方的な押し付けなど、子どもの成長を阻害する関わりも不適切保育とみなされることがあります。
⑥ハラスメント行為(園児間)への不適切な対応
園児同士のいじめやハラスメントを放置したり、適切に対応しないことも不適切保育とみなされる可能性があります。
(4)重大事故の対応・報告
園内で発生した事故は、その程度に関わらず、迅速かつ適切な対応が求められます。特に、死亡事故や重度の負傷を伴う事故は重大事故として扱われ、行政等の関係機関への報告義務や、保護者への説明責任が伴います。
①事故発生時の初期対応
事故発生時の緊急措置、救急車の手配、保護者への連絡など、初動の適切さがその後の展開を大きく左右します。
②関係機関への報告義務
重大事故が発生した場合、自治体や教育委員会、所轄庁などへの速やかな報告が義務付けられています。報告が遅れたり、内容に不備があったりすると、園の信頼を損ねるだけでなく、行政処分を受ける可能性もあります。
③保護者への説明・対応
事故の原因究明、再発防止策の説明、医療費や慰謝料に関する話し合いなど、保護者への誠実な対応が求められます。感情的になりやすい状況であるため、冷静かつ丁寧なコミュニケーションが不可欠です。一方で保護者からの不当な要求については応じないという毅然とした姿勢も要求される場面です。
④事故調査・原因究明
事故の原因を客観的に調査し、再発防止策を講じることが重要です。外部の専門家を交えた第三者委員会による調査が必要となる場合もあります。
⑤情報公開・マスコミ対応
重大事故の場合、マスコミからの取材や情報公開が求められることがあります。適切な情報公開の範囲や方法を誤ると、不必要な憶測を呼び、園のイメージを損なう可能性があります。
(5) 顧問弁護士による定期相談
日々の運営の中で生じる小さな疑問や懸念を、顧問弁護士に定期的に相談することで、大きなトラブルへの発展を未然に防ぐことができます。具体例を少し述べます。
①契約書のリーガルチェック
職員との雇用契約書、保護者との入園契約書、業務委託契約書など、各種契約書の法的有効性やリスクについて、事前にチェックを受けることができます。
②就業規則の改定・見直し
労働基準法の改正や社会情勢の変化に対応し、就業規則を常に最新の状態に保つためのアドバイスを受けられます。
③トラブル発生時の初動対応のアドバイス
実際にトラブルが発生した際、初期段階で弁護士に相談することで、事態の悪化を防ぎ、適切な対応策を講じることができます。
④各種規約・マニュアルの整備
保護者対応マニュアル、危機管理マニュアル、個人情報保護規約など、園運営に必要な各種規約やマニュアルの整備をサポートします。
⑤研修会の実施
職員向けのハラスメント研修、個人情報保護研修、危機管理研修などを弁護士に依頼することで、職員の法的知識を向上させ、トラブル発生リスクを低減できます。
2. トラブルを未然に防ぐためのポイント
トラブルを未然に防ぐためには、予防的な取り組みが不可欠です。
(1)明確なルールとマニュアルの整備
職員の労働時間、残業代の計算方法、ハラスメントに対する方針、保護者対応の手順、事故発生時の対応フローなど、園の運営に関するあらゆるルールを明確にし、文書化して職員に周知徹底することが重要です。これにより、解釈の齟齬を防ぎ、個人の判断に依存しない統一された対応が可能になります。特に、就業規則や雇用契約書は、労働問題における基本的な根拠となるため、法律に基づいた適切な内容であるか定期的に確認が必要です。
(2)職員への定期的な研修と教育
ハラスメント防止研修、個人情報保護研修、危機管理研修、保護者対応研修など、職員が業務を適切に行うための知識とスキルを習得できるような研修を定期的に実施しましょう。特に、不適切保育や重大事故を防ぐためには、職員一人ひとりの意識向上が不可欠です。具体的な事例を交えながら、何が不適切行為にあたるのか、どうすれば事故を防げるのかを具体的に学ぶ機会を設けることが効果的です。
(3)コミュニケーションの活性化と相談しやすい環境づくり
職員同士、職員と園長・主任、そして保護者との間のコミュニケーションを密にすることで、小さな問題が大きくなる前に気づき、対処することができます。定期的な面談、意見交換会の実施、相談窓口の設置など、心理的安全性の高い環境を整えることが重要です。特に、保護者からのクレームは、初期段階で傾聴し、共感を示すことで、深刻化を防ぐことができます。
(4)保護者との連携と情報共有の徹底
入園前の説明会や入園契約書、入園後の園だよりや連絡帳などを通じて、園の方針、保育内容、緊急時の連絡体制、料金体系など、保護者に対して正確かつ詳細な情報を提供しましょう。特に、アレルギー対応や持病など、個別の配慮が必要な事項については、書面で確認を取り、情報共有を徹底することが重要です。園と保護者との間で共通認識を持つことで、後のトラブルを未然に防ぐことができます。
(5)記録の徹底と証拠の保全
職員の労働時間、保護者とのやり取り、事故発生時の状況、不適切保育に関する情報など、園運営に関わるあらゆる情報は、日時、内容、対応者を明確にして記録に残しておくことが非常に重要です。例えば、保護者からのクレーム電話の内容や、不適切保育の疑いがある職員への指導内容など、後の紛争解決の際に重要な証拠となることがあります。デジタルデータだけでなく、必要に応じて書面でも保管し、適切な管理を行いましょう。
(6)専門家との連携(特に弁護士)
法律問題が発生する前に、弁護士と顧問契約を結ぶなどして、日常的に相談できる関係を築いておくことが最も効果的な予防策の一つです。法改正への対応や、就業規則の見直し、新しいサービスの導入など、様々な場面で法的リスクを事前に評価し、適切なアドバイスを受けることができます。
3. 幼稚園・保育園が法律問題等を弁護士に相談するメリット
幼稚園や保育園が法律問題に直面した際、弁護士に相談することには多大なメリットがあります。
(1)法的リスクの早期発見と予防
弁護士は、法律の専門家として、園が抱える様々な問題に潜む法的リスクを早期に発見し、適切な予防策を提案することができます。例えば、就業規則の不備や契約書のリスク、保護者対応の潜在的なトラブルなど、自力では気づきにくい問題点も指摘してくれるでしょう。これにより、問題が深刻化する前に対応できるため、将来的な紛争を未然に防ぎ、時間的・経済的な負担を大幅に軽減できます。
(2)迅速かつ適切な問題解決
万が一トラブルが発生してしまった場合でも、弁護士は法律に基づいた適切な解決策を迅速に提示し、実行をサポートします。例えば、労働問題であれば、労働審判や訴訟への対応、保護者との紛争であれば、交渉や調停、訴訟といった手続きを代理で行うことができます。専門家による介入は、感情的になりがちな当事者間の対立を冷静に収め、円満な解決へと導く可能性を高めます。
(3)経営の安定と信頼性の向上
法的トラブルは、園の評判を著しく低下させ、経営に大きな影響を与える可能性があります。弁護士が関与することで、透明性の高い適切な対応が可能となり、園の信頼性を維持・向上させることにつながります。また、法的リスクを適切に管理し、安心して運営できる体制を整えることで、経営の安定にも寄与します。特に、不適切保育や重大事故といった社会的に注目を集めやすい問題においては、弁護士の存在が園の姿勢を社会に示す上で重要となります。
(4)職員の安心感と業務効率の向上
弁護士が顧問として関わることで、職員は安心して業務に専念できるようになります。例えば、保護者からの過度な要求やハラスメントに悩む職員は、弁護士がバックについていることで精神的な支えを得られます。また、労働問題やハラスメントに関する相談窓口を弁護士に設けることで、職員が抱える不安を解消し、健全な職場環境の維持に貢献します。これにより、職員のモチベーション向上や離職率の低下にもつながります。
(5)多様な法律問題への対応
幼稚園や保育園の運営には、労働法、民法、個人情報保護法、児童福祉法など、多岐にわたる法律が関係します。弁護士はこれらの法律の専門家であり、様々な種類の法律問題に対応することができます。契約書の作成・チェックから、クレーム対応、事故対応、行政指導への対応、さらにはM&Aや事業承継に関する相談まで、園が直面しうるあらゆる法律問題に対して、包括的なサポートを提供することが可能です。
弁護士は単なる「トラブル解決屋」ではなく、「予防法務」の専門家でもあります。日常的な相談を通じて、法的リスクを管理し、健全な園運営をサポートする存在として、弁護士の活用は幼稚園・保育園にとって不可欠な時代となっています。
4 当事務所のサポート内容
具体的なサポート内容は顧問プランの詳細をご覧いただきたいのですが,月額5万円(税別)のプランで園において日常生じる問題への対応はほとんどカバーできると思います。
当事務所は幼稚園・保育園の顧問業務も多く行っておりますので園の実情やニーズに応じたきめ細やかな対応が可能です。
顧問税理士もいる,顧問の社労士もいる,そろそろ顧問弁護士を依頼したいという法人の経営者の皆様のニーズにお応えできると思います。
5 当事務所に依頼するメリット
当事務所は各弁護士が全ての業務を行い,そのようなジェネラリストの弁護士が集まっているという法律事務所ではなく各弁護士が担当する業務を集中して行うという地方都市では珍しいタイプの法律事務所です。このような事務所であるが故に各弁護士が集中して対応する業務においてはより迅速に,かつ,より適切なサービスを提供できていると考えております。会社の顧問弁護士業務については,その最たる分野だと思います。
宮崎県で幼稚園・保育園を運営されている法人の経営者の皆様,顧問契約をお考えの際には当事務所にご相談ください。
 文責 弁護士 浜田 諭
文責 弁護士 浜田 諭