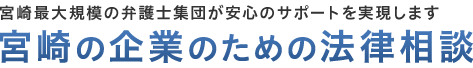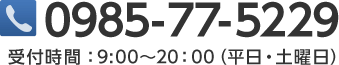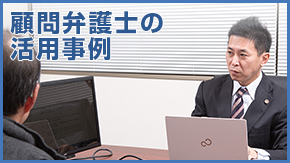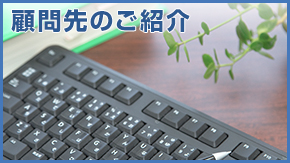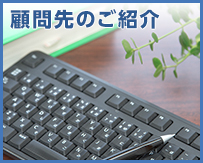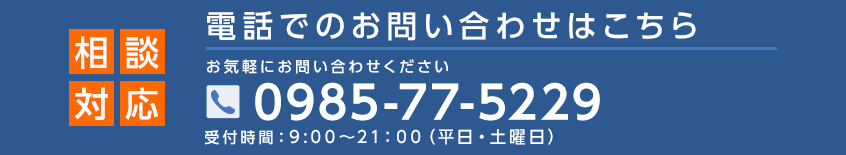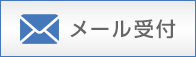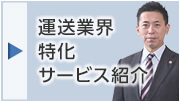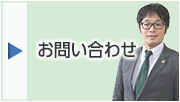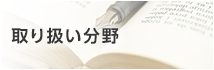入管法(入国管理法)関連手続きについて
在留資格認定証明制度
1 在留資格認定証明書制度とは?
在留資格認定証明書とは、査証の申請前に在留資格の該当性や上陸基準の適合性について法務大臣が事前に審査を行い、それぞれの要件を満たす場合に法務大臣が交付する証明書です。
この証明書の交付を受けた外国人は、査証(ビザ)の発給申請や上陸申請を行う場合、円滑かつ迅速に行われることになります。なお、在留資格認定証明書の有効期間は発行日から3か月であるため、発給後3か月以内に日本に入国しないと失効してしまいます。
2 在留資格認定証明書制度を利用した場合の流れ(代理人申請の場合)
ア 地方入国管理局等に対して在留資格認定証明書交付申請
イ 同局で該当性・適合性の査
ウ 同局より在留資格認定証明書交付
エ 在留資格認定証明書を本国にいる本人に送付
オ 在外公館で本人が在留資格認定証明書を提示して査証申請
カ 査証発給
キ 日本に入国し在留資格認定証明書を提出して上陸申請
3 上陸拒否の特例を受けるための活用方法
入管法第5条の2では上陸拒否の特例を定めていますが、その1つとして「当該外国人が在留資格認定証明書の交付・・・を受けた場合」が上げられます。在留資格認定証明書の発行において入国管理局が上陸拒否事由について一定の判断を経ているからです。
実務上、上陸拒否事由のある外国人について、在留資格認定証明書が交付されると当該上陸拒否事由のみによっては上陸を拒否しない旨の通知書が交付されます。その後、外国人は査証を取得し、査証付きの旅券、在留資格認定証明書、通知書を持参して上陸審査を受けることができます。
在留期間更新許可
1 在留期間更新許可申請とは?
外国人が、現に許可されている在留期間を更新することです。
在留期間を1日でも過ぎるとオーバーステイ扱いになってしまいます。オーバーステイになると、入国禁止期間が発生し、状況に応じて1年間、5年間、10年間日本に入国できなくなるので、注意が必要です。
更新許可申請は、在留期間満了日の2か月前から申請を行うことができます。ただし、在留期間の間際での申請の場合、更新が許可されない場合すみやかに出国する必要がありますので、時間的余裕を持って申請の準備をしなければなりません。
なお、やむを得ない事情でオーバーステイになってしまった場合、在留特別許可を受けることを検討することがなされる必要があります。
在留特別許可
1 在留特別許可とは?
退去強制事由に該当する外国人は、原則として日本から退去強制されることになります。しかし、法務大臣に異議の申出をすることで、特例として在留が許可されることがあります(在留特別許可)。在留特別許可がなされる場合、在留資格、在留期間の指定がなされることになります。
2 在留特別許可される場合
①永住許可を受けているとき
②かつて日本国民として日本に本籍を有したことがあるとき
③人身取引等により他人の支配下に置かれて日本に在留するものであるとき
④その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき
3 在留特別許可の留意点
在留特別許可は、法務大臣の自由裁量による判断とされています。そのため、在留特別許可はあくまで例外的な特例措置ですので、申請権が明確に認められているものではありません。ただし、「在留特別許可に関するガイドライン」が公表されており、不十分ながら一定の基準が示唆されています。
収容とは
1 収容
収容とは、オーバーステイ等の場合に入国管理局により一時的に身柄を拘束されることをいいます。
2 収容の種類
①収容令書による収容
収容令書に基づいて収容されるものです。期間は30日間以内とされており、やむを得ない事由があると認めるときは更に30日間延長できます。
②退去強制令書による収容
退去強制令書による収容です。「送還可能のときまで」となっており、期限の定めがなく、長期間収容が続くケースもあります。
3 収容からの解放手段
①仮放免許可申請、②退去強制令書の取消訴訟を提起した場合に執行停止の申立てをする方法になります。実務上は、①を行いつつ、②を同時並行して進めていくことになります。
仮放免とは?
1 仮放免とは
仮放免とは、収容されている外国人に病気その他やむを得ない事情がある場合に、職権または申請でその収容を一時的に停止して、一定の条件のもと身柄の拘束を解く措置のことです。
仮放免許可となった場合、多くの場合300万円以内の保証金の納付が必要とされます。
2 仮放免許可申請にどのような理由の主張が有効か
仮放免が許可されるか否かは、入管法に具体的に定められていませんが、考慮事項が仮放免取扱要領において定められているため、それを踏まえた申請を行うことが必要です。
とりわけ、仮放免の必要性(年齢、仕事、学校、病気、家族状況)、仮放免の相当性(審理状況、逃亡や証拠隠滅のおそれ)を主張する必要があります。なお、必要性との関係で①人身取引の被害者の疑いのある者、②未成年者、③傷病者等通院・入院等の必要のある者、④幼児・児童を監護養育している者、⑤その他社会的に弱者とみなされる者は有利に判断されることがありますので、積極的に主張すべきと考えられます。
3 仮放免許可申請における弁護士の有用性
弁護士が身元保証人となる場合あるいは弁護士が出頭に協力する旨の書面を提出する場合、仮放免の許可の判断や保証金の額、提出書類の関係で有利になる可能性があります。
そのため、仮放免許可申請を弁護士に依頼することに有用性があると思われます。
就労資格証明書とは
1 就労資格証明書
就労資格証明書とは,在留外国人の申請により,当該外国人が行える就労活動を法務大臣が証明する文書のことをいいます。
同証明書があることにより、雇用主が就職を希望する外国人が就労資格があるかを明確に確認できるうえ、外国人本人としても就職をスムーズに行えます。
2 就労資格証明書の留意点
同証明書はあくまでも利便性の向上のための任意の手段であり、就労資格証明書がないことによる雇用の差別等の不利益な扱いを禁止しています。
また、就労資格証明書の具体的な活用場面は、在留外国人が転職する場合です。就労資格証明書は、現在の在留資格の範囲内で働くことが可能であるかどうかを確認するために取取得することが多いのが実情です。つまり、転職後新たな勤務先で仕事に従事するときに、新たに従事する業務が「資格外活動の許可の範囲内」の業務内容であることを確認するために申請し、証明を受けることで安心して就労できることになるのです。
在留資格変更許可とは
1 在留資格変更許可
在留資格変更許可とは、在留外国人が、在留中に在留目的を変更したりする場合に、新たな在留資格へ変更の許可のことです。
2 具体例(一例)
①留学生が大学卒業後に就職する場合
②日本人配偶者との間で離婚した場合
3 在留資格変更許可の留意点
在留資格変更許可は「在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り」、許可されるものとされており、申請しても許可されるとは限らないことに注意する必要があります。
在留資格変更許可にあたっては、ガイドラインで判断基準が一定程度明確化されており、同基準に該当していることを主張するとともに、充足しないもので手当てが可能なものであれば対応する必要があります(未納分の納税等)。